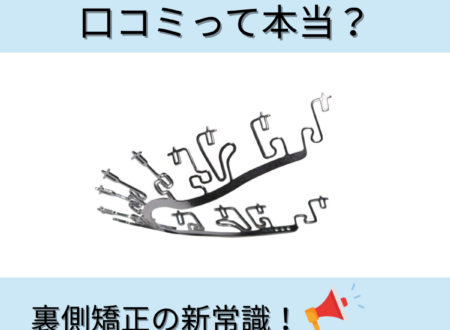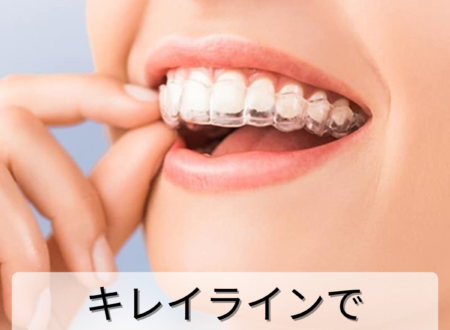- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

噛んだときに痛みがあり、治療を受けたいけれど痛みの原因や適切な治療法がわからない方も多いのではないでしょうか。
噛み合わせで痛みが出る原因は多岐にわたるため、自分の症状がどれにあてはまるのか、事前に把握しておくことが大切です。
この記事では、噛み合わせで痛みが出ることに悩んでいる方に向けて、以下の内容を解説します。
・噛み合わせで痛みが出る14の原因
・噛み合わせの異常を放置するリスク
・噛み合わせで痛みが出るときの対処法
・歯・噛み合わせの状態をセルフチェックする方法
噛み合わせの痛みを解消したいという方は、ぜひ参考にしてください。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
- 1. 噛み合わせで痛みが出る14の原因
- 1-1. 虫歯・歯周病
- 1-2. 習慣・癖
- 1-3. 歯の詰め物・被せ物の不適合
- 1-4. インプラントの不適合
- 1-5. 顎関節症
- 1-6. 不正咬合
- 1-7. 咬合性外傷
- 1-8. 親知らず
- 1-9. 抜歯後の噛み合わせのズレ
- 1-10. 知覚過敏
- 1-11. 歯のひび・亀裂
- 1-12. 根尖性歯周炎
- 1-13. 歯性上顎洞炎
- 1-14. 歯根膜炎
- 2. 噛み合わせの異常を放置するリスク
- 3. 噛み合わせで痛みが出るときの対処法
- 3-1. 歯列矯正
- 3-2. 咬合調整
- 3-3. 補綴治療
- 4. 歯・噛み合わせの状態をセルフチェックする方法
- 4-1. 口の開き具合のチェック
- 4-2. 唇のチェック
- 4-3. 前歯のチェック
- 4-4. 左右の噛み合わせのチェック
- 5. まとめ|噛み合わせで痛みが出るときは実績の豊富な歯科医院へ!
1. 噛み合わせで痛みが出る14の原因

噛み合わせで痛みが出る症状には、さまざまな原因が考えられます。
ここでは、虫歯やインプラントの不適合など、14個の主な原因について紹介します。
噛み合わせで痛みを感じている方は、あてはまるものがないかチェックしてみてください。
1-1. 虫歯・歯周病
虫歯や歯周病が原因で、噛んだときに痛みを感じているケースは多い傾向にあります。
そもそも虫歯とは、歯に付着した菌が表面のエナメル質を溶かす症状のことです。
一方、歯周病とは、歯垢がたまって歯茎が炎症を起こしている症状を指します。これらの症状は進行すると骨が溶けて歯が抜けたり、動いたりするようになるので、なるべく早めに歯科医院で適切な治療を受けましょう。
1-2. 習慣・癖
普段の習慣や癖が、噛み合わせを悪くするケースも少なくありません。
習慣や癖の具体例は、以下のとおりです。
・歯ぎしり
・食いしばり
・頬杖
・口呼吸
・横向き寝
・うつぶせ寝
特に、歯ぎしりや食いしばりは、歯がすり減ったり割れたりする原因にもなるため注意が必要です。また、無意識のうちに前歯を舌で押していることが原因で、噛み合わせが悪化するケースもあります。
1-3. 歯の詰め物・被せ物の不適合
虫歯治療のあとに、削った歯の部分を補うための詰め物・被せ物が合っていないことが原因で、噛み合わせで痛みを感じるケースがあります。
詰め物・被せ物の位置が高い、あるいは不均等に装着されていると特定の歯に負担がかかり、噛んだときに痛いと感じたり違和感を覚えたりすることにつながります。
劣化によって詰め物が徐々にすり減り、違和感に気付きにくいケースもあるので、定期的に歯科医院で診察してもらうことが大切です。
1-4. インプラントの不適合
インプラントとは、金属製の人工の歯根を埋め込み、人工の歯を再建する治療法のことです。インプラント治療の実施後、以下のようなことが要因で噛み合わせが悪くなるケースがあります。
・インプラントの位置が高い
・骨量が少なくインプラントが安定しない
・口腔ケアが不十分で炎症を起こしている
また、インプラント以外の歯が歯周病に冒され、不安定なために噛み合わせが悪化することもあります。
1-5. 顎関節症
顎関節症とは顎に関する病気の総称で、口を開くときや食べ物を噛むときに痛みを感じたり、関節の痛みで顎を大きく開けなかったりするなどの症状が見られます。
軽度の顎の痛みを感じる、あるいは噛むときに違和感を覚えるような場合は、歯列矯正で改善できる可能性があります。しかし、強い炎症を起こしていたり、精神的な要因で慢性化していたりする場合、歯列矯正での改善は難しいかもしれません。
関連記事
1-6. 不正咬合
不正咬合とは、噛み合わせ・歯並びが悪い状態のことです。噛み合わせ・歯並びが整っていないと、特定の歯に大きな負担がかかり、噛んだときの痛みにつながります。
不正咬合の例は、以下のとおりです。
・出っ歯
・受け口
・八重歯・叢生(そうせい)
・すきっ歯
・過蓋咬合(かがいこうごう)
叢生とは、歯が前後に重なりデコボコになっている状態を指し、過蓋咬合とは下の前歯に上の前歯が深く被っている状態を指します。
1-7. 咬合性外傷
咬合性外傷とは、特定の歯に大きな負担がかかり、歯の痛みや歯茎の炎症といった症状が出ている状態のことです。
主な症例は以下のとおりです。
・噛むと歯が痛い
・歯茎から血が出る
・冷たいものがしみる
・目の奥が痛む など
咬合性外傷になる原因として、歯ぎしりや食いしばり、噛み合わせ・歯並びのバランスが取れていないことが挙げられます。
1-8. 親知らず
親知らずは、10代後半から20代前半の頃に最後に生えてくる永久歯です。真っ直ぐに生えてくれば問題ありませんが、斜めや横向きに生えると、周囲の歯に悪影響をおよぼす可能性があります。
顎の付け根が痛んだり、奥歯が腫れたりする場合は、抜歯などの処置を検討したほうがよいでしょう。親知らずの抜歯費用は、医療機関や保険適用の有無で異なります。
関連記事
1-9. 抜歯後の噛み合わせのズレ
虫歯治療の一環として、抜歯するケースも少なくありません。ただし、抜歯後の歯を放置すると、歯並びの乱れや咀嚼する歯の偏りが発生して、噛み合わせが悪くなることがあるので注意が必要です。
抜歯後に歯並びが悪くなった場合は、なるべく早めに矯正歯科医師に相談して、適切な治療を受けましょう。
1-10. 知覚過敏
知覚過敏とは、冷たい飲食物や歯ブラシが歯に触れるだけで、一過性の痛みを感じる症状のことです。歯は本来、エナメル質という硬い組織が刺激に弱い象牙質を覆って守っているため、痛みを感じることはありません。
しかし、歯茎が下がったり、歯のひび・欠けが発生したりすると象牙質が露出し、外部からの刺激が痛みにつながります。なお、知覚過敏の治療では保険適用が可能です。
1-11. 歯のひび・亀裂
強く噛んで歯に負荷をかけたり、歯を強打したりすることで歯にひびや亀裂が生じると、しみるような痛みにつながるケースがあります。
また、歯の根元が割れる「歯根破折」の症状になると、破折したところから細菌が侵入し、噛んだときの痛みや周囲の歯茎の腫れにつながります。炎症の進行を防ぐため、抜歯治療を行なうことが一般的です。
1-12. 根尖性歯周炎
根尖性歯周炎とは、虫歯や打撲などで歯の神経が死んだ際に、歯根の先端に生じる炎症のことです。この症状を放置すると、膿がたまって歯槽膿漏になるケースもあるため注意しましょう。
根尖性歯周炎の治療では、感染した神経や細菌を取り除く「感染根管治療」を行ないます。場合によっては、1ヵ月以上の治療期間が必要です。
1-13. 歯性上顎洞炎
歯性上顎洞炎とは、副鼻腔の一つである「上顎洞」が歯の疾患により炎症を起こして膿がたまる症状のことで、蓄膿症とも呼ばれます。
神経を抜いた歯や神経が死んでいる歯の根元の炎症が、上顎の歯の上にある上顎洞へ広がることが原因で、治療では抜歯と炎症している上顎洞の洗浄を行なうのが一般的です。
なお、歯性が原因でないものは、単に「上顎洞炎」と呼ばれます。
1-14. 歯根膜炎
歯と骨の間にある歯根膜で炎症が生じる「歯根膜炎」になると、噛み合わせで痛みを感じることがあります。主な原因は、歯ぎしりや食いしばりによる歯への負荷や、歯と被せ物のすき間からの細菌感染などです。
歯ぎしりや食いしばりが原因の場合は、マウスピースの着用や噛み合わせの調整で改善が見込まれるでしょう。細菌感染が原因の場合は、患部に薬剤を注入し、詰め物をして対処します。
2. 噛み合わせの異常を放置するリスク

痛みの有無にかかわらず、噛み合わせが悪いまま放置すると、以下のような悪影響をおよぼす可能性があるので注意が必要です。
・顎関節症の悪化
・歯周病の悪化
・全身の不調
噛み合わせの異常を放置することで、顎に過剰な力がかかって顎関節症が悪化するおそれがあります。歯並びが悪化して口腔ケアが十分に行なえず、歯周病リスクが高まるケースも少なくありません。
また、異常な噛み合わせが全身の不調につながるケースもあります。
例えば、歯並びが原因で咀嚼が不十分だと、消化器官に負担がかかってしまいます。さらに、首・肩周りに刺激が伝わることで、頭痛や肩こりの原因になるケースもあるため注意が必要です。
3. 噛み合わせで痛みが出るときの対処法

次に、噛み合わせで痛みを感じるときの主な治療方法について解説します。自分に合った治療法を把握すれば、スムーズに対処しやすくなるので、ぜひチェックしてください。
3-1. 歯列矯正
噛み合わせで痛みを感じる原因が、前述の出っ歯や受け口といった不正咬合の場合、歯列矯正で改善が見込まれます。歯列矯正には、「マウスピース矯正」と「ワイヤー矯正」の2つの代表的な方法があります。
マウスピース矯正は、透明なプラスチック製のマウスピースを装着して徐々に歯列を整える方法です。矯正が目立ちづらい、痛みが少なく口腔ケアがしやすい、食事の制限が少ないなどのメリットがあります。
一方、ワイヤー矯正は金属の矯正装置を装着して歯列を整える方法で、重度の症例にも対応できることがメリットです。ただし、マウスピース矯正と比べて矯正装置が目立ちやすく、痛みを感じるケースがあることに留意が必要です。
関連記事
3-2. 咬合調整
咬合調整とは、噛み合わせた際のバランスを調整するために、歯を最小限削る治療のことです。この治療を受けることで、以下の効果が期待できます。
・口が開きやすくなる
・顎関節症の改善・予防を図れる
・歯の破折・欠けを防止できる
・咬合性外傷のリスクを減らせる
なお、咬合調整は基本的な噛み合わせの治療ですが、自由診療の扱いとなり保険適用できないことに留意が必要です。
3-3. 補綴治療
補綴(ほてつ)治療とは、虫歯などで失った歯の部分を補う治療全般のことです。例えば、歯を抜いたまま放置している場合、噛み合わせや歯並びに悪影響を与える可能性が高まります。
そのため、被せ物や入れ歯、インプラントなどの補綴治療を施し、口腔環境を整える必要があります。抜歯した際は、何らかの症状が出る前に早めに補綴治療を受けるようにしましょう。
4. 歯・噛み合わせの状態をセルフチェックする方法

ここからは、噛み合わせが正常な状態かを確認できるセルフチェックの方法を4つ紹介します。
いずれも簡単にできるものばかりなので、ぜひ参考にしてください。
4-1. 口の開き具合のチェック
口を大きく開けたときに、縦にそろえた3本の指が入らない場合、顎関節に負荷がかかっているおそれがあります。
また、口を開けてカクッと音がするときは、顎関節症の初期症状の可能性があるため注意が必要です。現状では痛みがなくても、早めに病院を受診することをおすすめします。
4-2. 唇のチェック
唇の閉じ具合は、鏡の前に立ってリラックスした状態でチェックします。
唇を閉じた状態で以下にあてはまる場合、噛み合わせが悪い可能性があります。
・唇を閉じきれずに前歯が見える
・下唇で上唇が隠れる
・下の唇を噛んでしまう
上記の状態にあてはまるときは、早めに病院で診てもらいましょう。
4-3. 前歯のチェック
一般に、奥歯を噛み合わせたときに、下の前歯に上の前歯が2~3mm被さっている状態が理想とされています。
そのため、「上の前歯が深く被さっていて下の歯が見えない」「上の前歯よりも下の歯が前に出ている」といった状態は、悪い噛み合わせです。
4-4. 左右の噛み合わせのチェック
左右の噛み合わせのバランスは、割り箸を使って確認できます。横向きにした割り箸を奥歯で噛んだとき、水平になれば噛み合わせは均等です。割り箸が傾いているときは、噛み合わせのバランスが崩れている可能性があります。
5. まとめ|噛み合わせで痛みが出るときは実績の豊富な歯科医院へ!

噛み合わせで痛みが出る原因は、虫歯・歯周病や習慣・癖、顎関節症などさまざまです。噛み合わせの異常を放置すると、症状の悪化や全身の不調につながるおそれもあるため、適切な治療を早めに受けることが重要です。
不正咬合が原因で噛み合わせの痛みを感じている場合は、矯正治療で治せる可能性があります。痛みが少なく、目立ちにくいマウスピース矯正を検討している方は、ぜひポータルサイト「ウィ・スマイル」をご活用ください。
当サイトなら、マウスピース矯正治療を実施している最寄りのクリニックを手軽に検索でき、Web予約も可能です。
矯正歯科医師が丁寧に診察したうえで、治療期間や治療回数、治療費をお伝えしますので、まずはお近くのクリニックをチェックしてみてはいかがでしょうか。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/