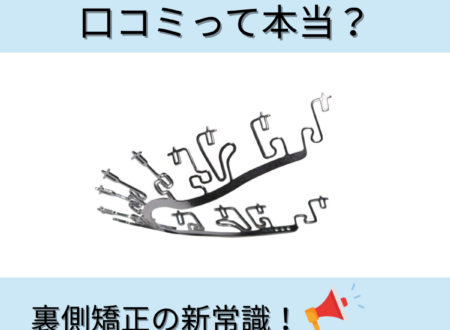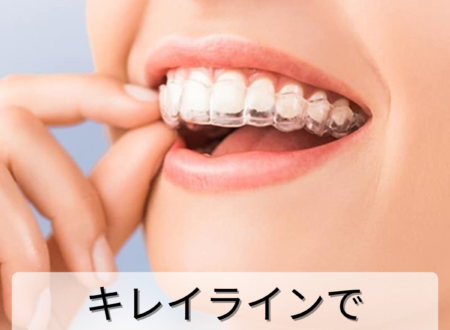- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

子供がなかなか指しゃぶりをやめられず、不安や悩みを抱えている保護者の方は少なくありません。
特に「指しゃぶりは口内の健康にどのような影響を与えるのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
指しゃぶりは歯並びの乱れを引き起こす可能性があるほか、虫歯・歯周病のリスクを高めたり、滑舌に影響を与えたりするおそれもあります。可能であれば早めにやめさせたほうがよいでしょう。
本記事では、長引く指しゃぶりが子供に与える影響や、無理なくやめさせるための工夫、指しゃぶりが原因で歯並びに影響が出た場合の矯正治療についても解説します。
矯正治療が可能な年齢や費用の目安も併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
- 1. 赤ちゃんの指しゃぶりはいつまで続く?
- 2. 指しゃぶりが長引くことによる影響
- 2-1. 歯並びが悪化する可能性がある
- 2-2. 虫歯や歯周病のリスクが高まる
- 2-3. 滑舌が悪化する可能性がある
- 3. 指しゃぶりの原因
- 3-1. 吸啜反射によるもの
- 3-2. 眠い・安心したい
- 3-3. 手で遊んでいる
- 3-4. 歯茎のかゆみや違和感
- 3-5. 癖になっている
- 4. 指しゃぶりをやめさせる方法
- 4-1. 手や指を使った遊びをする
- 4-2. 積極的なスキンシップでストレスや不安を軽減させる
- 4-3. 絆創膏や塗り薬を使う
- 4-4. なぜ指しゃぶりをしてはいけないのか伝える
- 5. 歯並びの矯正をするならいつから?
- 5-1. 6~8歳くらいで始めるのが一般的
- 5-2. 費用はクリニックによってさまざま
- 6. まとめ|指しゃぶりは歯の健康に影響あり!早めに対処を
1. 赤ちゃんの指しゃぶりはいつまで続く?
赤ちゃんが指しゃぶりを始める時期には個人差がありますが、一般的には生後2〜3ヵ月頃から見られるようになります。
実際には胎児期から指しゃぶりをしていることもあり、生後3ヵ月頃までの指しゃぶりは生理的な行動とされています。
この時期の指しゃぶりは、赤ちゃんにとって精神的な安定をもたらす重要な役割を果たしているため、無理にやめさせる必要はありません。
過度に気にすることなく、自然な成長の一環として見守る姿勢が望ましいでしょう。
しかし、指しゃぶりが長期間続くと口内の健康に悪影響をおよぼす可能性があります。
特に4歳以降になると歯並びへの影響が懸念されるため、子供が自然にやめられない場合は、3歳頃から保護者による工夫で徐々にやめさせるのが理想です。
2. 指しゃぶりが長引くことによる影響
1~2歳頃の指しゃぶりは、歯並びや口の健康に大きな影響を与えることはないとされています。
しかし、前述のとおり、指しゃぶりが4歳以降まで続くと歯並びや滑舌、口腔機能に影響をおよぼす可能性が高まるため注意が必要です。
ここでは、長引く指しゃぶりが与えるおもな影響について解説します。
2-1. 歯並びが悪化する可能性がある
指しゃぶりは指を口蓋(上の歯の裏側)に押し当てて強く吸う行為であり、口内の圧力が高まることで歯列や顎の成長に影響をおよぼします。
長期間続くと、以下のような不正咬合(噛み合わせの異常)を引き起こす可能性があります。
| 不正咬合 | 特徴 |
|---|---|
| 出っ歯 | 上の前歯が前方に突き出る状態で、唇を閉じづらくなることもある。 |
| 受け口 | 下の歯が上の歯より前に出る噛み合わせで、顔つきに影響することもある。 |
| 開咬 | 上下の前歯が噛み合わず隙間ができる状態で、発音や食べ物の噛み切りに支障が出ることもある。 |
| 交差咬合 | 一部の上下の歯が左右にずれて噛み合う異常で、顎の成長に左右差が出る可能性がある。 |
これらの不正咬合を放置すると、虫歯や歯周病、口臭などのリスクが高まります。
また、しっかり噛んで食事をすることが難しくなるため、胃腸への負担につながる可能性もあるでしょう。
さらに、成長期の子供の身体や脳の発達にも悪影響をおよぼすことが懸念されます。
関連記事
出っ歯の直し方を徹底解説!矯正法・費用・期間までわかりやすく紹介
受け口(反対咬合)の治し方|子どもと大人で異なる治療法と費用の全て
2-2. 虫歯や歯周病のリスクが高まる
指しゃぶりが長期間続くと、口が常に開いた状態になりやすく、口呼吸が習慣化するケースがある点にも注意が必要です。
口呼吸は口内を乾燥させ、唾液の量を減少させる要因となります。
唾液には殺菌作用があることから、虫歯や歯周病の予防に重要な役割を果たしています。
そのため、唾液が減ることで口内の細菌が繁殖しやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まることをしっかりと認識しておきましょう。
また、指しゃぶりによって歯並びが悪くなると、歯磨きで汚れを十分に落とすことが難しくなり、磨き残しが増えることで口内トラブルのリスクがさらに上昇します。
2-3. 滑舌が悪化する可能性がある
指しゃぶりによって開咬になると、舌が正しい位置に収まりにくくなり、「タングスラスト(舌突出癖)」と呼ばれる舌足らずな発音になりやすくなります。
特に「サ行」や「タ行」など、舌先を使う音が不明瞭になる傾向があり、成長後も滑舌に悩むケースは少なくありません。
また、指しゃぶりが原因で舌の位置に癖(舌癖)がつくと、発音だけでなく、舌の筋力や動きにも影響が出ることがあります。
これにより、発声の練習機会が減少し、言語発達の遅れにつながる可能性も指摘されています。
3. 指しゃぶりの原因

子供の指しゃぶりにはさまざまな原因があり、複数の要因が複雑に絡んでいることも少なくありません。
ここでは、一般的によく見られる指しゃぶりの原因を参考としてご紹介します。
3-1. 吸啜反射によるもの
赤ちゃんは生まれつき吸啜(きゅうてつ)反射を持っています。
これは母親の乳首あるいは哺乳瓶など、口元に触れたものに自然と吸いつく反応のことで、指しゃぶりもその延長と考えられます。
吸啜反射は母乳や哺乳瓶から栄養を摂るための本能的な動きであり、たとえお腹が空いていなくても口元に触れた指を吸うのは自然な行動です。
そのため、生後数ヵ月の赤ちゃんに対しては無理にやめさせる必要はなく、見守る姿勢が基本です。
3-2. 眠い・安心したい
指しゃぶりは、眠気を感じたときや不安・緊張を覚えたときなど、子供が安心感を得たい場面でよく見られます。
退屈なときや、親の注意を引きたいときなどにも見られる傾向があり、情緒的な安定を求める行動の一つといえるでしょう。
3-3. 手で遊んでいる
赤ちゃんは成長とともに自分の手の存在に気付き、徐々に動きをコントロールできるようになります。
その過程で、指しゃぶりを通じて手の感覚を確かめたり、遊びの一環として指を口に入れたりすることがあり、これは正常な発達の過程であるといえるでしょう。
このような場合は、発達の一部として自然な行動です。
代わりにおもちゃなどを渡してあげると、指しゃぶりからスムーズに卒業できる可能性があります。
3-4. 歯茎のかゆみや違和感
歯の生え始める時期には、歯茎にむずがゆさや違和感を覚えることがあります。
その不快感を紛らわせるために、指をしゃぶって刺激を与えていることも少なくありません。
この時期は、おもちゃを噛む行動も増える傾向があります。
安全性の高い歯固めや噛めるおもちゃを用意して、そっと見守るとよいでしょう。
3-5. 癖になっている
4歳以降も指しゃぶりが続く場合、習慣として定着している可能性が高いです。
不安や退屈を感じたときに指しゃぶりで安心できた、ストレスを発散できたというこれまでの経験をもとに、無意識のうちに繰り返されている状態といえるでしょう。
このような癖は、寂しさや退屈を紛らわせる手段として残っていることが多いほか、気分転換やストレス発散の一環として指しゃぶりをしてしまうケースも見られます。
習慣化している場合は、段階的な働きかけが必要です。
4. 指しゃぶりをやめさせる方法

指しゃぶりがすっかり習慣化している場合、やめさせるのは簡単ではありません。
しかし、子供の気持ちに寄り添いながら根気強く取り組むことで、少しずつ改善していくことが可能です。
ここでは、無理なく指しゃぶりを卒業させるための具体的な方法を紹介します。
4-1. 手や指を使った遊びをする
日中に指しゃぶりをやめられない場合は、手や指を使った遊びを積極的に取り入れるのがおすすめです。
例えばブロックやパズル、積み木、折り紙、粘土などの遊びでは、指先を使うことで自然と口から指が離れ、習慣の改善につながります。
また、手遊び歌やしりとりなど、指しゃぶりをしているとできない遊びも効果的です。
4-2. 積極的なスキンシップでストレスや不安を軽減させる
指しゃぶりの背景にストレスや不安がある場合は、スキンシップを通じて安心感を与えることが有効です。
寝る前にぎゅっと抱きしめる、話をたくさん聞く、絵本を一緒に読む、手をつないで寝るなど、心のつながりを感じられる時間を意識的に増やしましょう。
安心感を得られると指しゃぶりに頼る必要がなくなり、自然と卒業できる可能性が高まります。
4-3. 絆創膏や塗り薬を使う
指しゃぶりする指に絆創膏を巻いたり、指しゃぶり対策専用の強い苦味のあるマニキュアを爪に塗ったりする方法もあります。
ただし、この方法は効果に個人差があることを覚えておきましょう。
無理やり絆創膏を取ってしまったり、苦味に慣れてしまって指をしゃぶり続けたりする子供もいるため、反応を見ながら慎重に取り入れることが大切です。
併せて指しゃぶりに関する絵本を活用することで、子供の意識を変えるきっかけになることもあります。
4-4. なぜ指しゃぶりをしてはいけないのか伝える
年齢が上がり、ある程度会話が成立するようになった子供には、「なぜ指しゃぶりがダメなのか」をやさしく説明することも大切です。
「歯並びが悪くなる」「虫歯になりやすくなる」といった具体的な理由をわかりやすく伝え、理解を促しましょう。
ちなみに、指しゃぶりをしているのを見つけたときに叱ったり、無理に口から指を引き抜いたりするのは逆効果です。
「どうして指しゃぶりはダメなんだっけ?」と問いかけるようにすると、子供が自分で考えるきっかけになります。
5. 歯並びの矯正をするならいつから?
指しゃぶりの影響で歯並びが悪くなった場合、将来的に歯列矯正が必要になることがあります。
歯並びの問題は虫歯や歯周病のリスクを高めるだけでなく、顎の発達や顔貌、発音にも影響するため、早期の相談が大切です。
では、実際に何歳頃から矯正治療を始めるのが適切なのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。
5-1. 6~8歳くらいで始めるのが一般的
歯列矯正は、6〜8歳頃に始めるのが一般的です。
この時期は顎の成長が活発で、永久歯への生え変わり時期でもあるため、噛み合わせの土台をしっかりと整えるのに最適といえます。
「まだ小さい子供に矯正治療をするのは不安」と感じる方もいるかもしれませんが、小児矯正には以下のようなメリットがあります。
・顎の成長を利用できるため、抜歯を避けられるケースが多い
・早期に噛み合わせを整えることで、顔立ちや滑舌、発音への悪影響を効果的に防げる
・成長期に合わせた治療ができるため、大人の矯正よりも負担が少なく済む
また、小児矯正には5~10歳頃に行なう「一期矯正(歯がきれいに並ぶスペースづくり)」と10歳~中学生以降に行なう「二期矯正(歯を正しい位置に並べる)」があります。
それぞれ目的や方法が異なるため、歯科医院へ早めに相談すると安心です。
5-2. 費用はクリニックによってさまざま
小児矯正治療の費用は、症状の程度、治療の範囲、装置の種類、クリニックの方針などによって大きく異なります。
以下は一般的な費用の目安です。
| 使用する装置 | 費用総額目安 |
| 床矯正(取り外し式) | 約10万~30万円 |
| ワイヤー矯正(ブラケット) | 約30万~60万円 |
| マウスピース矯正 | 約40万~60万円 |
※上記は一期矯正の目安であり、二期矯正を含む場合はさらに費用がかかることがあります。
なお、小児矯正は医療費控除の対象にもなることもあり、治療前に確認しておくと安心です。
費用や治療方針は歯科医院によって異なるため、複数のクリニックで相談・比較することをおすすめします。
関連記事
小児矯正の費用相場まとめ|装置別の違い・医療費控除・支払い方法まで解説
6. まとめ|指しゃぶりは歯の健康に影響あり!早めに対処を
赤ちゃんの指しゃぶりは、成長過程で自然に見られる行動です。
しかし、長期間続くと歯並びの乱れや発音への影響、虫歯のリスクにつながる可能性があります。まずは原因や子供の気持ちを理解し、無理なくやめさせていくことが大切です。
もし指しゃぶりによって子供の歯並びが乱れてしまった、あるいは歯並びに不安を感じている場合は、早めに専門家へ相談してみましょう。
「ウィ・スマイル」では、全国の矯正歯科医院の中から、厳しい基準をクリアした信頼性の高い医院のみを掲載しています。
安心してお子さまの治療を任せられる歯科医を探したい方は、ぜひ一度「ウィ・スマイル」にアクセスしてみてください。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/