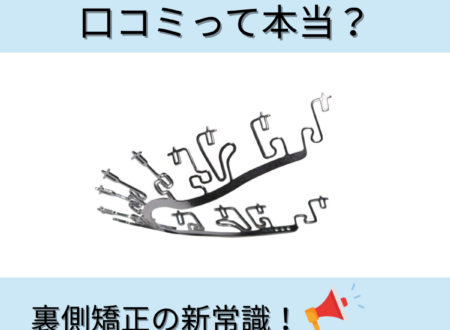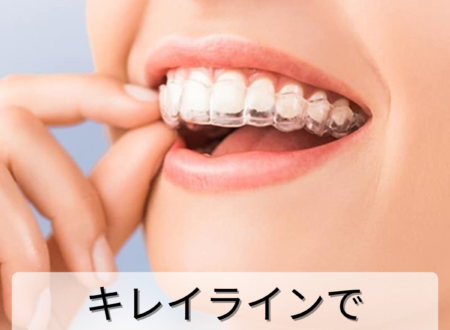- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

「毎日しっかり歯を磨いているつもりなのに、なぜかすぐに歯石ができてしまう…。」
そんな悩みを抱えている人は、実は少なくありません。歯石は、一度できてしまうと通常の歯ブラシでは落とせないほど硬くなり、歯の表面に強くこびりつきます。放置すればするほど蓄積し、見た目の清潔感を損なうだけでなく、歯周病や口臭の原因にも直結します。
さらに、歯石の表面はザラザラしており、新たなプラーク(歯垢)がつきやすい状態をつくってしまいます。そのため「歯石が歯石を呼ぶ」といった悪循環に陥り、気づいたときには歯茎の炎症や出血など、より深刻なトラブルへと進行してしまうこともあります。
この記事では、そんな歯石がなぜできやすいのか、そしてどんな人が特に注意すべきなのかを紹介していきます。また、歯石を増やさないための毎日のケア方法や、今日からすぐに始められる予防のコツも紹介します。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
- 1. 歯石ができやすい人の特徴
- 1-1. 唾液の分泌が少ない(ドライマウス傾向)
- 1-2. 食後の歯磨きが遅い/不十分
- 1-3. 口呼吸・喫煙習慣がある
- 1-4. 歯並びが悪く、磨き残しが多い
- 1-5. タンパク質・糖分の多い食生活
- 2. 歯石とは?どうしてできるの?
- 2-1. 歯石の正体は「硬くなった歯垢(プラーク)」
- 2-2. どのくらいで歯石になる?(2〜3日で硬化)
- 2-3. 歯石が歯茎や虫歯に与える影響
- 3. 歯石ができやすい原因を科学的に解説
- 3-1. 唾液中のカルシウムとリン酸が多い体質
- 3-2. 口内のpHバランスがアルカリ性に傾くと石灰化が進む
- 3-3. プラークを放置する時間が長いと硬化しやすい
- 3-4. 歯石が付きやすい部位(下前歯の裏・上奥歯の外側)
- 4. 歯石ができやすい人は虫歯や口臭に要注意!
- 4-1. 歯石の下に潜むプラークが虫歯の原因に
- 4-2. 歯石が歯茎を刺激し、歯周病リスクを高める
- 4-3. 歯石表面の凹凸が口臭を悪化させる
- 5. 歯石を防ぐには?毎日のセルフケア方法
- 5-1. 食後30分以内に歯磨きを習慣化
- 5-2. 歯ブラシ+フロス+洗口液の三段ケア
- 5-3. 水分をこまめに摂り、唾液分泌を促す
- 5-4. 甘い・粘着性の食べ物を控える
- 5-5. 定期的な歯科クリーニング(3〜6ヶ月ごと)
- 6. 歯医者で行う歯石除去とホームケアの違い
- 6-1. スケーリングとは?超音波で歯石を除去
- 6-2. PMTCでプラークごと徹底クリーニング
- 6-3. 自宅ケアとの違いと、両方を続ける意味
- 7. 歯石ができやすい人の“ライフスタイル別アドバイス”
- 7-1. デスクワーク中心の人「口呼吸・水分不足に注意」
- 7-2. コーヒー・お茶をよく飲む人「着色と歯石のダブル対策」
- 7-3. 矯正中・マウスピース使用者 「歯石が付きやすい“死角”に注意」
- 7-4. 喫煙者「唾液量低下とヤニ汚れのWリスク」
- 8. まとめ|歯石が付きやすい人ほど“早めの予防習慣”がカギ!
1. 歯石ができやすい人の特徴

歯石は、毎日の歯磨きでは取りきれなかった歯垢が硬くなってできるものです。同じようにケアをしていても、歯石ができやすい人とそうでない人がいます。人によって歯石のつき方やスピードには大きな差があります。
生活習慣や唾液の質、磨き方、体質など、さまざまな要因が関係しているため、自分の傾向を知ることが歯石予防の第一歩です。ここでは、歯石ができやすい人に共通する“特徴”には何があるか整理してみましょう。
1-1. 唾液の分泌が少ない(ドライマウス傾向)
唾液には、口の中を洗い流す「自浄作用」や、歯を修復する「再石灰化作用」があります。そのため、唾液量が少ないと歯垢が残りやすく、やがて歯石化が進行してしまいます。
唾液の分泌が少ない理由としては、加齢やストレス、薬の副作用などがあります。
ドライマウス傾向チェックリスト
・口の中がよく乾く
・朝起きたときに舌が張り付く
・口臭が気になる
・水をよく飲むようになった
1つでも当てはまる場合は、唾液の分泌低下を疑いましょう。
1-2. 食後の歯磨きが遅い/不十分
プラーク(歯垢)は、細菌が集まってできる粘り気のある膜のことです。これをそのまま放置しておくと、わずか48時間ほどで石のように硬くなり、歯石へと変化してしまいます。
「朝は時間がなくてサッと磨くだけ」「夜だけ磨く」など、毎日の歯磨き習慣が乱れると、歯石ができるリスクは一気に高まります。
正しい歯磨きのタイミングとしては、食後30分以内がおすすめです。
関連記事
1-3. 口呼吸・喫煙習慣がある
無意識に口で呼吸している人は、常に口の中が乾燥しやすくなっています。唾液には細菌の繁殖を抑える働きがあるため、乾燥状態が続くとプラークが作られやすく、歯石の温床になります。
また、喫煙習慣がある人は、ニコチンによって血流が悪くなるうえ、唾液の分泌量も減少します。その結果、歯の表面に歯垢や汚れが付着しやすくなります。さらに、ヤニ汚れが歯の表面をざらつかせ、歯石の土台となってしまうこともあります。
【口呼吸チェック】
次の項目に3つ以上当てはまる場合、無意識的に口呼吸になっている可能性があります。
・朝起きたときに口が乾いている
・いびきや寝息が大きいと言われる
・唇がよく乾燥する・口角が切れやすい
・口を閉じていると顎に力が入る
・集中時やスマホ使用中に口が開いている
無意識の口呼吸は、口内が乾燥して歯石や虫歯、口臭を引き起こす原因になります。以上のようなサインがある人は要注意です。日中の鼻呼吸を意識し、就寝時は加湿や口テープで口を閉じる習慣をつけましょう。
1-4. 歯並びが悪く、磨き残しが多い
歯並びが乱れていると、歯の重なりや凹凸にプラークがたまりやすく、磨き残しの原因になります。歯ブラシの毛先が届きにくい部分に汚れが残ることで、歯石や虫歯のリスクも高まります。
マウスピース矯正で歯列が整うと、ブラッシングがしやすくなり、口内を清潔に保ちやすくなります。
1-5.タンパク質・糖分の多い食生活
歯石の原因となる細菌は、糖やタンパク質をエサにして増殖します。甘いお菓子や清涼飲料水、またプロテインなど高タンパクな食事をとる機会が多い現代では、プラークが形成されやすくなります。
特に、砂糖を多く含む飲み物をダラダラ飲む習慣は、口の中を常に酸性状態にしてしまい、歯垢が歯石に変わるスピードを早めてしまいます。
砂糖入り飲料は水やお茶に置き換え、間食にはナッツやチーズなど歯にやさしい食品を選ぶと効果的です。
2. 歯石とは?どうしてできるの?

「歯石=歯にこびりついた汚れ」と思われがちですが、その正体を知ると予防法も明確になります。歯石ができるメカニズムと、放置したときのリスクについて見ていきましょう。
2-1. 歯石の正体は「硬くなった歯垢(プラーク)」
歯石とは、歯垢(プラーク)が唾液中のカルシウムやリン酸と反応して硬化したものです。歯垢(プラーク)は歯の表面だけでなく、歯と歯茎の境目や歯間の狭い隙間にも入り込みます。そのため、歯ブラシの毛先が届きにくく、毎日のブラッシングだけでは完全に除去できません。
さらに、時間が経つとバイオフィルムと呼ばれる膜状の構造になり、細菌が守られてしまうため、歯科での専門的なクリーニングが必要になります。
2-2. どのくらいで歯石になる?(2〜3日で硬化)
プラークが歯石化するまでの時間は早く、わずか2〜3日です。磨き残しを放置すると、すぐに硬化してしまいます。
2-3. 歯石が歯茎や虫歯に与える影響
歯石は歯茎を押し下げ、炎症や出血を引き起こすことで、歯周病の進行を促します。
また、歯石の表面はざらついており、細菌が付着しやすくなるため、汚れがたまりやすい悪循環が生まれます。その結果、虫歯や口臭のリスクも高まり、口内の健康全体に影響を及ぼします。
3. 歯石ができやすい原因を科学的に解説

なぜ自分だけ歯石が多いのか?それには体質的な要素だけでなく、口の中の化学的なバランスや生活習慣が深く関係しています。
歯石ができる背景には、体質や生活習慣、口腔環境の3つの要因があります。
3-1. 唾液中のカルシウムとリン酸が多い体質
唾液の中には、もともと歯を修復したり、口内の酸を中和したりするためのカルシウムやリン酸といったミネラル成分が含まれています。これらは本来、歯の健康を守るために欠かせない重要な成分です。
しかし、人によってはこのミネラル成分が非常に多く含まれており、その結果、歯垢(プラーク)が短時間で石灰化し、歯石へと変わりやすくなることがあります。いわば、唾液の中のカルシウムやリン酸が“歯石の材料”になってしまう状態です。
この体質は、ある程度遺伝的な要因や体質の個人差によって決まる部分もあります。さらに、飲み水の硬度(カルシウムやマグネシウムを多く含む硬水)、乳製品や小魚などミネラルを多く摂取する食習慣も影響すると言われています。
3-2. 口内のpHバランスがアルカリ性に傾くと石灰化が進む
私たちの口の中は、食事や唾液の働きによって常にpH(酸性・アルカリ性)のバランスが変化しています。通常は、食後に酸性に傾いた口内環境を、唾液が時間をかけて中和し、健康な状態へと戻しています。
しかし、口内のpHが高い環境では、歯垢(プラーク)の中のカルシウムやリン酸が沈着しやすくなり、石灰化が急速に進行します。その結果、歯石が形成されやすくなるのです。
3-3. プラークを放置する時間が長いと硬化しやすい
歯石ができるかどうかは、単に「歯磨きの回数」だけでなく、どれだけの時間プラーク(歯垢)を口の中に放置しているかによって大きく左右されます。
プラークは、歯の表面に付着してからおよそ48時間で硬化し、歯石へと変化していきます。つまり、夜だけ磨くなど、1日1回だけの歯磨きでは、磨き残しがそのまま硬化してしまう可能性が高いです。
3-4. 歯石が付きやすい部位(下前歯の裏・上奥歯の外側)
口の中でも特定の部位に歯石がつきやすいところというのがあります。とくに多いのが、下前歯の裏側と上奥歯の外側です。これは、唾液腺の開口部が近くにあるためです。下前歯の裏側には舌下腺や顎下腺、上奥歯の外側には耳下腺の出口があり、常に唾液が分泌されているため、その周辺ではカルシウムやリン酸などのミネラル成分が沈着しやすくなります。
また、これらの部位は歯ブラシが届きにくく、磨き残しが起こりやすい場所でもあります。とくに下前歯の裏は歯の重なりが強いことも多く、歯垢が溜まりやすいのです。
| 歯石が付きやすい部位 | 唾液腺の種類 (唾液の出る場所) | 唾液腺の位置 (口の中のどこにあるか) | 付きやすい理由・特徴 |
|---|---|---|---|
| 下の前歯の裏側 (下顎前歯の裏) | 舌下腺・顎下腺 | 舌の下、下あごの内側 | 唾液が直接当たりやすく、カルシウム成分が沈着しやすい |
| 上の奥歯の外側 (上顎臼歯の外側) | 耳下腺 | 上の奥歯の外側、頬の内側 | 唾液の出口(ステノン管)が近く、外側面に歯石が付きやすい |
| その他の歯周囲 | 小唾液腺 | 口唇・頬・舌の粘膜面全体 | 局所的に唾液が当たる箇所で軽度の付着が起こる場合も |
4. 歯石ができやすい人は虫歯や口臭に要注意!

歯石自体は硬い沈着物ですが、その下には細菌が密集しています。つまり歯石は「菌の温床」。そんな歯石と虫歯・歯周病・口臭にはどんな関係があるでしょうか。
4-1. 歯石の下に潜むプラークが虫歯の原因に
先述したように、歯石の下にはプラークが潜んでおり、そこへは歯ブラシの毛先が届きません。そのため、歯石を放置すると虫歯が進行してしまいます。
さらに、歯石が長期間残ると、虫歯菌が酸を出し続け、歯の内部まで侵食して神経に達するおそれもあります。
関連記事
4-2. 歯石が歯茎を刺激し、歯周病リスクを高める
歯茎の炎症(歯肉炎)は、放置すると骨を溶かす歯周病へ進行します。出血や腫れ、口臭などが初期サインです。
この原因となるのも、歯石の縁にたまった歯石です。歯石が歯茎をじわじわと刺激し、進行すると歯を支える骨が下がり、最終的には歯がぐらつくほどのダメージを受けることもあります。
歯石を除去すると、歯茎に直接刺激を与えていた細菌や硬い汚れがなくなるため、炎症が落ち着きます。炎症が収まると血流や組織の修復が促され、歯茎の腫れが引いて引き締まることで、健康な歯周組織が回復していきます。
4-3. 歯石表面の凹凸が口臭を悪化させる
歯石の表面は凸凹でざらざらしており、ニオイの元となる細菌が付着しやすいです。舌苔や喫煙、ドライマウスが重なると、さらに悪臭の原因になります。特に歯の裏側や歯間部に付着した歯石は自分では気づきにくく、慢性的な口臭の原因になりやすい点にも注意が必要です。
口臭ケアは「根本原因(歯石)」の除去が必須であると言えます。
5. 歯石を防ぐには?毎日のセルフケア方法

歯石を防ぐカギは、「できる前に落とす」ことです。日々の歯磨きや生活習慣を少し工夫するだけで、歯石の形成スピードを大きく抑えられます。
今日から始められる実践的なセルフケア方法を紹介します。
5-1. 食後30分以内に歯磨きを習慣化
プラークは硬化する前に除去するのがポイントです。よくある誤解として、「食後すぐに磨かない方がいい」というものがあります。食後は口内が酸性に傾き歯の表面が一時的に軟らかくなっているため、すぐにブラッシングすると歯を傷める可能性があるためです。
ただし、あまりにも長く待つのはよくありません。食後30分ほど待ってから磨くか、まず水やうがいで酸を中和してから歯磨きを行うのが安心です。
忙しい人でも続けやすい時短ケアとして、おすすめなのは寝る前に歯ブラシ+フロスをセットで行う「ながらケア」です。
5-2. 歯ブラシ+フロス+洗口液の三段ケア
歯ブラシでは届かない歯間部の汚れをフロスで除去し、仕上げに洗口液で口内全体を清潔に保ちましょう。この三段ケアを習慣化することで、歯石の原因となるプラークの蓄積を大幅に減らせます。特に就寝前のケアを丁寧に行うと、睡眠中の細菌繁殖を防ぐ効果が高まります。
関連記事
5-3. 水分をこまめに摂り、唾液分泌を促す
唾液は最強の「天然の洗浄液」と言われています。水分が不足すると唾液の分泌量が減り、口内の自浄作用が低下します。唾液にはプラークや酸を洗い流す働きがあるため、分泌が減ると細菌が増えやすくなり、歯石の沈着が進みます。
水分をこまめにとり、ガムを噛む・舌マッサージを行うなど、唾液分泌を促す工夫をしましょう。口が乾く状態が続くと、細菌が増えやすくなり、歯石や口臭のリスクが高まります。
5-4. 甘い・粘着性の食べ物を控える
キャラメルやグミなどの粘着性食品は歯に残りやすく、歯石の温床になります。糖分が長時間歯に残ると、プラーク中の細菌が酸を出し、歯の表面を徐々に溶かしていきます。
完全に食べないなどNG食品にするのではなく、頻度やタイミングのコントロールをしていきましょう。また、食後には必ず水うがいをしたり、キシリトールガムなどを活用したりするのもいいでしょう。
5-5. 定期的な歯科クリーニング(3〜6ヶ月ごと)
一度付いた歯石は自宅では除去できず、プロによるクリーニングが唯一の確実な方法です。歯科では、スケーリングで歯石を取り除き、研磨(ポリッシング)やフッ素塗布で歯面をツルツルに整えるPMTC(プロフェッショナルクリーニング)が行われます。
3〜6ヶ月ごとを目安に定期的に受けることで、口内の健康を守ることができます。美容メンテナンス感覚で受けるといいでしょう。
6. 歯医者で行う歯石除去とホームケアの違い

どんなに丁寧に磨いても、歯石は少しずつ蓄積していきます。完全に取り除くには、専門家による定期的なメンテナンスが欠かせません。
ここでは、歯科医院で行う歯石除去の方法と、自宅ケアとの違いを解説します。
6-1. スケーリングとは?超音波で歯石を除去
スケーリングとは、超音波の振動で歯石を取り除く治療です。痛みはほとんどなく、1回30分程度で終わります。歯茎の下に隠れた歯石も除去できます。
保険診療でスケーリングを行う場合、費用としては1回あたり おおよそ 2,000〜3,000円程度(3割負担) が目安です。
施術中は「キーン」という音や水しぶきがありますが、歯や歯茎を傷つけることはありません。定期的に行うことで、歯周病や口臭のリスクを大きく減らすことができます。
6-2. PMTCでプラークごと徹底クリーニング
プロフェッショナルクリーニングでは、専用の器具でプラークやステイン、バイオフィルムまで除去します。
プロフェッショナルクリーニングの流れ(PMTC)
1.口腔内チェック:歯や歯茎の状態、汚れの付着部位を確認します。
2.スケーリング(歯石除去):超音波や専用器具で、歯茎の上や下の歯石を除去します。
3.研磨(ポリッシング):専用ペーストで歯の表面を磨き、ステインや着色を除去します。
4.仕上げとフッ素塗布:歯面をツルツルに整え、再付着防止のためにフッ素を塗布します。
施術後は歯面がツルツルになり、汚れの再付着も防げます。
6-3. 自宅ケアとの違いと、両方を続ける意味
自宅ケアは再付着防止のため、歯科ケアは歯石の根本除去のために行います。両方を継続することで、歯石ゼロの状態を保てます。どちらか一方だけでは、時間とともに汚れが蓄積し、歯石や炎症の再発につながりやすくなるからです。
7. 歯石ができやすい人の“ライフスタイル別アドバイス”

歯石のつき方には、ライフスタイルや職業による傾向もあります。
仕事や習慣に合わせ、生活パターン別のアプローチ方法を取り入れることで、より効率的に歯石の再発を防ぐことができます。
7-1. デスクワーク中心の人「口呼吸・水分不足に注意」
長時間のPC作業では、集中して口が開きやすくなり、無意識の口呼吸になりやすくなります。こまめな水分補給や、意識して鼻呼吸を行うこと、合間に軽く首や肩のストレッチをすることで口内の乾燥を防げます。
オフィスでもできる歯石対策としては、間食後のうがいや、フロス・マウスウォッシュの活用することが挙げられます。オフィスでも手軽に口内環境を整えられるように工夫してみましょう。
7-2. コーヒー・お茶をよく飲む人「着色と歯石のダブル対策」
着色汚れが歯石と結びつくと見た目の悪化にもつながります。コーヒーやお茶をよく飲む人は、飲んだ後のうがいやストローの使用で対策をしましょう。定期的に歯科でPMTCを受け、着色と歯石を同時にケアするのもいいでしょう。
7-3. 矯正中・マウスピース使用者 「歯石が付きやすい“死角”に注意」
矯正中の方は、装置周囲は磨き残しが多く、湿度変化で細菌が繁殖しやすくなります。歯石が付きやすい“死角”となるので、口腔ケアは矯正専用ブラシを使って行いましょう。
また、マウスピース使用者は、専用のリテーナー洗浄を習慣化しましょう。
矯正で歯並びが整えば、磨きやすさにつながります。磨きやすい口内環境は、プラークや歯石の蓄積を防ぎます。ウィ・スマイルでは、歯並びを整えることで、「ケアしやすくなり、歯の健康を守りやすくなる」という考えを大切にし、一人ひとりが毎日の口腔ケアを続けやすい状態づくりをサポートしています。
7-4. 喫煙者「唾液量低下とヤニ汚れのWリスク」
喫煙に含まれるタールやニコチンは、歯石の沈着を促進するとともに、唾液の分泌量を減少させます。唾液が減ることで口内の自浄作用が低下し、プラークや歯石がたまりやすい環境が生まれます。
そのため、喫煙者こそ定期的な歯科クリーニングが特に重要であり、禁煙サポートやホワイトニングを受けることが、歯の健康と見た目の改善へとつながるでしょう。
8. まとめ|歯石が付きやすい人ほど“早めの予防習慣”がカギ!

歯石は一度付いてしまうと自力では取れません。だからこそ、「歯石をゼロにする」よりも「増やさない習慣」を意識することが大切です。唾液量や生活習慣を整え、毎日のセルフケアと定期的な歯科クリーニングを組み合わせることで、清潔で健康な口元を長く保つことができます。
ウィ・スマイルでは、マウスピース矯正を通じて“磨きやすい歯並び”づくりと“予防ケア”の両立をサポートしています。まずは気軽に相談してみてください。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/