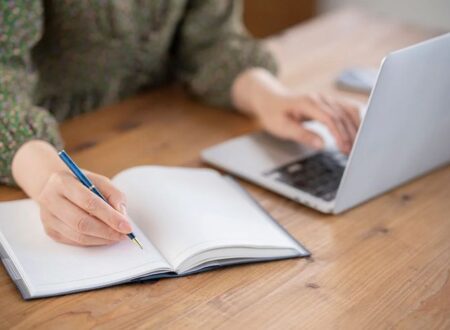- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

歯ぐきの健康を守るために重要なのが「歯周ポケット」のケアです。
しかし、「歯周ポケットって何?」「掃除しないとどうなるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
歯周ポケットを適切にケアしないと、口臭や歯ぐきの腫れ、歯周病の進行など、さまざまなトラブルを引き起こす原因になります。さらに、放置することで全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあるため、適切な対策が必要です。
本記事では、歯周ポケットの基本知識から、自宅でできる掃除のコツ、歯科でのプロフェッショナルケアまで詳しく解説します。
正しい知識を身につけて、健康な口内環境を保ちましょう!
- 1. 歯周ポケットとは?
- 1-1. 歯周ポケットが深くなる主な原因
- 2. 歯周ポケットを放置するとどうなる?
- 2-1. 歯茎の腫れや痛み
- 2-2. 口臭
- 2-3. 知覚過敏
- 2-4. 歯のぐらつき
- 2-5. 全身の健康への影響
- 3. 自宅でできる!歯周ポケットケアの正しい方法
- 3-1. 歯ブラシで歯と歯茎の境目を重点的に磨く
- 3-2. 歯磨き粉を適切に選ぶ
- 3-3. デンタルフロス&歯間ブラシを使う
- 3-4. マウスウォッシュを活用する
- 3-5. やってはいけないNG習慣
- 4. 専門家によるプロフェッショナルケアの重要性
- 4-1. 歯周ポケットの測定と治療
- 5. 歯周病予防には自宅と歯科のダブルケアが重要
- 5-1. 歯周病予防に効果的な食べ物・栄養素
- 5-2. 健康な歯ぐきを保つための食習慣
- 6. まとめ:歯周ポケットは早期対策がカギ!
1. 歯周ポケットとは?

歯周ポケットとは、歯と歯茎の間にできる溝のことです。この溝は、健康な状態では1~3mm程度の深さですが、細菌が溜まり炎症が起こると、徐々に深くなります。
深さが4mm以上になると歯周病の兆候、
6mm以上では重度の歯周病と診断されることがあります。
歯周ポケットが深くなる主な原因は、日々のブラッシングで取りきれなかった汚れの蓄積です。この汚れを放置すると、細菌が増殖し、歯ぐきに炎症を引き起こすことでポケットがさらに深くなってしまいます。
歯周ポケットが深くなるにつれて、酸素の少ない環境を好む歯周病菌が増えやすくなり、結果として歯周病が悪化するという負のサイクルに陥ってしまいます。
1-1. 歯周ポケットが深くなる主な原因
歯周ポケットが深くなる主な原因には、以下のようなものがあります。
プラーク(歯垢)の蓄積:
適切なブラッシングができていないと、細菌が増殖し炎症を引き起こす。
歯石の蓄積:
プラークが固まり歯石になると、歯ぐきの奥へ炎症が広がりやすくなる。
喫煙:
タバコに含まれる有害物質が歯ぐきの血流を悪化させ、炎症を引き起こしやすくする。
ストレスや不規則な生活:
免疫力の低下により歯周病のリスクが高まる。
歯周ポケットの深さは、歯科医院で測定できます。3mmを超えると要注意、5mm以上になると本格的な歯周病のリスクが高まるため、早めの対策が必要です。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
2. 歯周ポケットを放置するとどうなる?

歯周ポケットが深くなると、以下のような症状が現れる可能性があります。
2-1. 歯茎の腫れや痛み
歯周ポケットが深くなると、そこに溜まった汚れや細菌が歯茎に炎症を引き起こします。
炎症が進むと歯茎が赤く腫れ、触れると痛みを感じることがあります。さらに進行すると、歯茎からの出血が見られることもあります。
この状態を放置すると、炎症が周囲の組織にも広がり、腫れや痛みが悪化していきます。
2-2. 口臭
歯周ポケット内で増殖した細菌が、食べ物のカスや血液を分解する過程で悪臭を放つガスを発生させます。
この口臭は、通常の歯磨きでは取り除くのが難しく、特に深い歯周ポケットがある場合には慢性的な口臭の原因となります。自覚しにくい場合も多いため、周囲から指摘されて気づくこともあります。
2-3. 知覚過敏
歯周ポケットが深くなると、歯茎が炎症により下がり始め、歯の根元(象牙質)が露出します。
象牙質には無数の細かい管があり、その中を通じて冷たいものや熱いもの、酸味の強い食べ物などの刺激が神経に伝わりやすくなります。
その結果、冷たい水を飲んだり、アイスを食べたりするときに、キーンとした不快感を感じるようになります。
2-4. 歯のぐらつき
歯周病が進行すると、歯を支える土台である歯槽骨が細菌によって溶かされてしまいます。
歯槽骨は歯をしっかりと固定する役割を持つため、これが減少することで歯が不安定になり、ぐらつきを感じるようになります。歯槽骨が大きく損なわれると、最終的には歯が抜け落ちてしまうリスクが高まります。
2-5. 全身の健康への影響
歯周病の原因となる細菌は、血流に乗って全身を巡ることで、以下のような疾患を引き起こす可能性があります。
糖尿病:
歯周病があると血糖値のコントロールが難しくなる。
心疾患・脳卒中:
歯周病菌が血管内に入り込み、動脈硬化を引き起こすリスクがある。
誤嚥性肺炎:
高齢者の場合、口内の細菌が気道に入り、肺炎の原因となる。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
3. 自宅でできる!歯周ポケットケアの正しい方法

自宅でもできるセルフケアは、歯周ポケットの進行を防ぐために非常に重要です。
ここでは、自宅でできる歯周ポケットの基本的なケア方法を紹介します。
3-1. 歯ブラシで歯と歯茎の境目を重点的に磨く
歯ブラシを使う際は、45度の角度で歯と歯茎の境目に当てることがポイントです。力を入れすぎず、細かく動かすことで歯周ポケットの汚れを効率的に取り除けます。
★おすすめアイテム
・ワンタフトブラシ
狭い部分や奥歯など、通常のブラシでは届きにくい場所の掃除に最適です。
3-2. 歯磨き粉を適切に選ぶ
歯磨き粉の量が多すぎると、泡立ちや清涼感で磨き残しに気づかないことがあります。1~2cm程度の量を使い、泡立ちが少ないジェルタイプがおすすめです。
★効果的な成分
・殺菌成分
細菌の増殖を抑制。
・抗炎症成分
歯茎の炎症を予防。
3-3. デンタルフロス&歯間ブラシを使う
歯ブラシだけでは届かない歯の間の汚れをしっかり落とすことは、歯周ポケットケアにおいて非常に重要です。
デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、汚れの除去率を大幅に向上させることができます。
★種類と特徴
・デンタルフロス
糸状の清掃用具で、狭い歯間の汚れを取り除くのに適しています。歯と歯の間に通してスライドさせることで、プラークや食べ物のカスをしっかり除去します。
・歯間ブラシ
歯間ブラシは、小さなブラシが付いた清掃用具で、広めの歯間の掃除に向いています。歯と歯の間にスムーズに挿入し、ブラシを前後に動かすことでプラークや汚れを効果的に除去できます。初めて使う場合は、歯科医師や歯科衛生士に相談して最適なサイズを教えてもらうと安心です。
・持ち手付きのY字型
フロス部分を保持するための持ち手が付いているタイプで、初心者や手先が不器用な方に最適です。Y字型の持ち手は奥歯にも届きやすく、初めて使う方でも簡単に取り扱えます。
★形状による選び方
・I字型
前歯などの直線的な部分を掃除しやすい形状。初心者にも使いやすいです。
・L字型
奥歯や歯列が複雑な箇所に適しており、奥まった部分にも届きやすい構造になっています。
3-4. マウスウォッシュを活用する
マウスウォッシュは口臭予防だけでなく、細菌の増殖を抑える効果があり、歯周ポケットのケアに役立ちます。
ただし、マウスウォッシュの使用だけでは汚れを完全に取り除くことはできないため、日常のブラッシングやフロスと併用することが大切です。
マウスウォッシュの選び方
殺菌成分入りのものを選ぶ
塩化セチルピリジニウム(CPC)やクロルヘキシジン配合のものが効果的。
アルコールの有無を確認
アルコール入りは爽快感があるが刺激が強いため、口内が敏感な方はノンアルコールタイプを選ぶ。
フッ素配合のものを活用
歯の再石灰化を促し、歯周病とむし歯の予防に役立つ。
正しい使い方のポイント
・歯磨き後に30秒ほど口をすすぐ。
・すすいだ後は30分間飲食を控える。
・朝晩の歯磨き後に継続して使用すると効果的。
3-5. やってはいけないNG習慣
・強い力でゴシゴシ磨く → 歯ぐきを傷つけ、逆に炎症を悪化させる。
・歯間ブラシのサイズが合っていない → 大きすぎると歯ぐきを傷つけ、小さすぎると効果が薄い。
・うがいだけで済ませる → マウスウォッシュの使用は補助的な役割であり、ブラッシングやフロスを併用しないと汚れは落ちない。
・歯ブラシを長期間使用する → 毛先が広がった歯ブラシは汚れを落とす力が低下するため、1ヶ月に1回は交換する。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
4. 専門家によるプロフェッショナルケアの重要性

自宅でのケアでは取り切れない歯周ポケットの汚れや歯石を除去し、健康な口内環境を維持するためには、歯科医院での専門的なケアが不可欠です。
歯科医院では、歯周病の進行度を診断し、適切な治療や予防策を提供します。
4-1. 歯周ポケットの測定と治療
歯周ポケットの測定方法
歯周ポケットの深さを測定するために、歯科医院では「プロービング検査」を行います。これは、専用のプローブ(細い器具)を使用して歯と歯ぐきの間の隙間の深さを測定するもので、以下の基準で診断されます。
| 歯周ポケットの深さ | 状態 |
| 1~2mm | 健康な歯ぐき |
| 3mm | 軽度の歯周炎の可能性 |
| 4mm以上 | 中等度以上の歯周病の疑い |
| 6mm以上 | 重度の歯周病で治療が必要 |
4mmを超えると、歯周病の進行が疑われるため、適切な治療を受ける必要があります。
歯周ポケットの専門的なクリーニング
歯周病の進行度に応じて、以下のような専門的な治療が行われます。
スケーリング(歯石除去)
歯の表面や歯ぐきの下に付着した歯石や細菌を除去。
超音波スケーラーや手用スケーラーを使用し、歯周ポケット内の清掃を徹底。
ルートプレーニング(歯根の滑沢化)
歯根の表面を滑らかにして、細菌の再付着を防ぐ。
歯周ポケットが深い場合に行われる処置。
レーザー治療(重度の場合)
炎症のある歯周ポケット内の細菌を除去し、歯ぐきの回復を促す。
痛みが少なく、出血も少ないため、患者の負担を軽減。
定期的な歯科検診の重要性
歯周病は初期段階ではほとんど自覚症状がなく、気づかないうちに進行する病気です。以下のような症状がある場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。
・歯ぐきが赤く腫れている
・ブラッシング時に出血する
・口臭が気になる
・歯がぐらつく感じがする
定期的な検診とクリーニングを受けることで、歯周病の進行を防ぎ、健康な歯ぐきを維持することができます。自宅でのケアでは、歯周ポケットの奥深くに蓄積した汚れを完全に取り除くことは難しいため、定期的な歯科クリニックでのクリーニングが必要です。
プロのケアを受けることで、歯周病の進行を抑え、健康な歯ぐきを維持することができます。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
5. 歯周病予防には自宅と歯科のダブルケアが重要

歯周病を防ぐためには、日々のセルフケアと歯科クリニックでの専門的なケアを組み合わせることが不可欠です。
毎日の適切なブラッシングやデンタルフロスの使用に加え、生活習慣の改善や食生活の見直しも重要なポイントとなります。
ここでは、歯周病予防に役立つ食事や栄養素について詳しく解説します。
5-1. 歯周病予防に効果的な食べ物・栄養素
口腔内の健康を維持するためには、バランスの取れた食事が不可欠です。以下の栄養素を意識的に摂取することで、歯周病のリスクを軽減することができます。
・ビタミンC(抗酸化作用・歯ぐきの健康維持)→ 柑橘類(レモン、オレンジ、グレープフルーツ)、ピーマン、ブロッコリー
ビタミンCは、歯ぐきの健康を維持し、炎症を抑える効果があります。歯周病の初期症状である歯ぐきの腫れや出血を防ぐために、日々の食事に取り入れると良いでしょう。
・カルシウム(歯や骨を強化)→ 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、豆腐
歯を支える骨を強化するために、カルシウムの摂取は欠かせません。特に歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶けやすくなるため、十分なカルシウム摂取が重要です。
・ポリフェノール(抗菌作用・抗炎症作用)→ 緑茶、赤ワイン、カカオ含有量の高いチョコレート、ブルーベリー
ポリフェノールには抗菌作用があり、口内の細菌の増殖を抑える効果があります。特に緑茶に含まれるカテキンは、歯周病の予防に有効とされています。
・オメガ3脂肪酸(抗炎症作用)→ サバ、サーモン、イワシ、アマニ油、チアシード
オメガ3脂肪酸には抗炎症作用があり、歯ぐきの腫れや炎症を軽減する効果があります。魚やナッツ類を積極的に食事に取り入れることで、歯周病リスクを抑えることができます。
・ビタミンD(カルシウム吸収促進)→ 卵黄、キノコ類、鮭、いわし
ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける働きを持ち、歯と歯ぐきを強化する役割を果たします。日光を浴びることでも生成されるため、適度な日光浴も併せて行うと良いでしょう。
・乳酸菌(口内環境を整える)→ ヨーグルト、納豆、キムチ、ぬか漬け
乳酸菌は口内の善玉菌を増やし、歯周病の原因となる悪玉菌の繁殖を抑える効果があります。特に発酵食品を継続的に摂取することで、口腔内環境の改善が期待できます。
5-2. 健康な歯ぐきを保つための食習慣
日々の食生活において、以下のポイントを意識すると、歯周病予防に役立ちます。
よく噛んで食べる
よく噛むことで唾液の分泌が促され、口内の細菌が洗い流されやすくなります。
砂糖の摂取を控える
砂糖の過剰摂取は、細菌の繁殖を助長し、歯周病の進行を早める可能性があります。
水分をしっかり摂取する
口の中が乾燥すると細菌が増えやすくなるため、適度に水を飲むことが大切です。
アルコールや喫煙を控える
アルコールやタバコは、歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病を悪化させる要因となります。
歯周病予防は、日々のケアと生活習慣の改善が鍵となります。
セルフケアだけでなく、歯科クリニックでの定期検診も併せて行うことで、健康な歯ぐきを維持しましょう。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
6. まとめ:歯周ポケットは早期対策がカギ!

歯周ポケットの放置は、単に口腔トラブルを引き起こすだけでなく、全身の健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。歯ぐきの腫れや歯のぐらつき、口臭だけでなく、歯周病が進行すると糖尿病や心疾患、さらには誤嚥性肺炎などのリスクを高めることも指摘されています。
毎日のセルフケアでは、正しいブラッシング、デンタルフロスや歯間ブラシの活用、マウスウォッシュの併用が重要です。しかし、自宅でのケアだけでは歯周ポケットの奥深くに蓄積した汚れを完全に除去することは難しいため、定期的に歯科クリニックでのクリーニングを受けることが推奨されます。
早期対策を行うことで、歯ぐきの健康を維持し、歯を長持ちさせることが可能になります。少しでも歯ぐきの違和感や出血が気になる場合は、自己判断せずに専門家の診察を受けるようにしましょう。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/