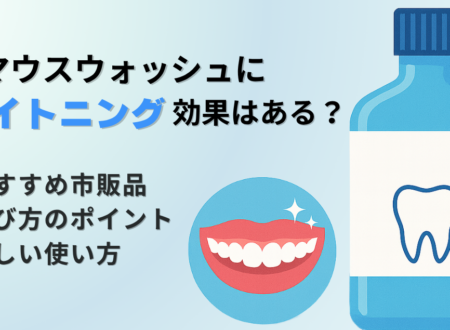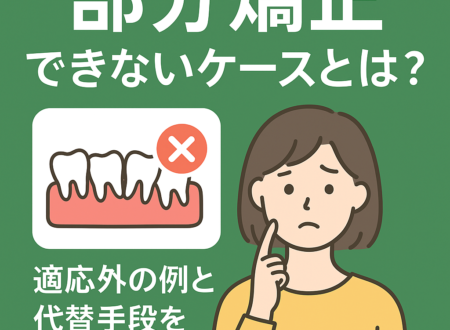- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

歯列矯正は高額な費用がかかるイメージがありますが、実は健康保険が適用されるケースもあることをご存じでしょうか。
歯列矯正は保険が適用されない「自由診療」になるのが一般的です。 しかし、症例によっては保険が適用される場合もあります。
この記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。
・歯列矯正が保険適用となる条件
・保険適用となる3つのケース
・保険の適用を受けるための流れと手続き
・保険適用と自由診療の費用の違い
・保険適用されない場合に矯正費用を抑える3つの方法
歯列矯正の保険適用についてしっかり理解したうえで、矯正治療を始めましょう。
- 1. 歯列矯正は基本的に保険適用外?まず知っておきたい前提知識
- 2. 歯列矯正で保険適用される3つのケースとは?
- 2-1. 厚生労働大臣が定める先天性疾患がある場合
- 2-2. 永久歯の萌出不全による咬合異常がある場合
- 2-3. 顎変形症の外科的矯正治療の場合
- 2-4. 学校健診で「歯列・咬合の異常」を指摘された場合は矯正相談が保険適用になる
- 3. 保険適用を受けるための流れと手続き
- 3-1. 「指定医療機関」での診察
- 3-2. 精密検査と診断書の取得
- 3-3. 保険証・紹介状など必要書類の準備
- 3-4. 保険機関による診断書の審査
- 3-5. 審査通過後に治療開始
- 4. 自由診療と保険適用で費用はどれくらい違う?
- 4-1. 自由診療の場合の費用イメージ
- 4-2. 保険適用された場合の費用イメージ
- 5. 保険適用されない場合でも矯正費用を抑える3つの方法
- 5-1. 医療費控除を活用する
- 5-2. デンタルローンの利用
- 5-3. クレジットカードで分割払いを利用する
- 6. 保険適用を目指す前に知っておくべき2つの注意点
- 6-1. 保険適用のために無理な治療計画を立てない
- 6-2. 保険適用に必要な手続きや書類は煩雑
- 7. 歯列矯正の保険適用に関するよくある質問
- Q1. マウスピース矯正は絶対に保険が使えない?
- Q2. 保険適用の医院はどこで探せますか?
- Q3. 保険が使えない矯正でも、医療費控除は受けられますか?
- Q4. 顎変形症かどうかはどこで診断されますか?
- 8. まとめ|歯列矯正の保険適用は条件次第!早めの相談が安心
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
1. 歯列矯正は基本的に保険適用外?まず知っておきたい前提知識

まずは、歯列矯正における保険適用の基本について解説します。
医療機関での治療は、健康保険が適用されて自己負担が一部で済む「保険診療」と、保険が適用されず全額自己負担となる「自由診療」 に分けられます。
歯列矯正は基本的に自由診療に分類され、健康保険は適用されません。歯並びを整える目的が、病気の治療というよりも、見た目を良くするための審美的側面が強いと考えられているためです。費用を自身で全額負担することになるため、歯列矯正は高額になる傾向があります。
ただし、すべての歯列矯正が自由診療というわけではありません。
厚生労働省が定めた疾患や、顎の外科手術をともなう場合など、医学的に歯列矯正が必要と認められる特別なケースでは、健康保険が適用されます。
歯列矯正が保険適用となる具体的なケースについて、このあと詳しく解説します。ご自身の症状が当てはまるか、ぜひチェックしてください。
2. 歯列矯正で保険適用される3つのケースとは?

「どのような場合に保険が適用されるの?」と気になる方のために、実際に保険適用される3つのケースをご紹介します。
●厚生労働大臣が定める先天性疾患がある場合
●永久歯の萌出不全による咬合異常がある場合
●顎変形症の外科的矯正治療の場合
また、学校の健診で「歯列・咬合の異常」を指摘された場合の矯正相談についても解説します。
2-1. 厚生労働大臣が定める先天性疾患がある場合
1つ目は、厚生労働大臣が定める先天性疾患がある場合です。さまざまな疾患が保険適用となっており、約2年に一度の保険診療報酬の改定で、疾患の追加や疾患名の標記見直しが行なわれます。
2024年の改定では、唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)、ダウン症候群、ゴールデンハー症候群など、66の先天性疾患が保険適用の対象となりました。
参照:日本矯正歯科学会「矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは」
このうちの一つ、唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)とは、口唇または口蓋に裂のある先天性疾患の総称です。
上顎の発達不全により歯列不正や不正咬合が生じることがあるため、乳児期から永久歯が生える時期まで、状態や成長に応じた手術や歯列矯正を行ないます。医療保険の対象となるため、早めに保険医療機関に相談しましょう。
2-2. 永久歯の萌出不全による咬合異常がある場合
2つ目は、永久歯萌出不全(えいきゅうしほうしゅつふぜん)の場合です。
これは、通常6歳頃から生え始めて12歳頃に生えそろう永久歯が、生えてこない症状を指します。「顎が小さいため歯が生えるスペースがない」「歯茎が厚いため生えてこられない」「先天的に歯が欠如している」など、原因はさまざまです。
歯が1本あるいは2本足りないケースは少なくありませんが、保険適用となるのは、前歯の永久歯が3本以上生えない場合で、埋伏歯開窓術が必要な症例 です。
気になる場合は、早めに保険医療機関に相談しましょう。
2-3. 顎変形症の外科的矯正治療の場合
3つ目は、顎変形症の外科的矯正治療を行なう場合です。顎変形症とは「上下の顎の骨が大きくずれている」「骨格の歪みが原因で、顔が左右対称でなくなる」といった症状により、噛み合わせが悪くなる「不正咬合」が起こる病気です。
顎変形症は、幼少期にはわからず成長するにつれて症状が出るケースもあります。顎離断などの外科的矯正手術が必要な場合には保険適用となるため、気になる方は保険医療機関で診断を受けましょう。
2-4. 学校健診で「歯列・咬合の異常」を指摘された場合は矯正相談が保険適用になる
2025年度の診療報酬改定により、学校健診で「歯列・咬合の異常」を指摘された場合、歯科矯正相談が保険適用となりました。
学校健診の結果が記載された「健康診断の結果のお知らせ」を持参した児童・生徒が対象で、専門医に相談する費用に保険が適用されます。ここでいう「歯列・咬合」とは、歯並びや噛み合わせを指します。
ただし、保険が適用されるのは学校健診で指摘された項目に関する矯正相談のみであり、実際の矯正治療全体が保険適用になるわけではない点に注意が必要です。
学校健診の結果を受けて不安を感じたら、まずは医療機関に相談してみましょう。
3. 保険適用を受けるための流れと手続き

ここまで紹介してきた歯列矯正が保険適用されるケースに該当しても、正しい手続きを踏まなければ保険は適用されません。
ここでは、保険適用を受けるために必要な流れとポイントをわかりやすく解説します。大まかな流れは以下のとおりです。
① 「指定医療機関」での診察
② 精密検査と診断書の取得
③ 保険証・紹介状など必要書類の準備
④ 保険機関による診断書の審査
⑤ 審査通過後に治療開始
詳しく見ていきましょう。
3-1. 「指定医療機関」での診察
保険適用の歯列矯正を受けるには、厚生労働省の基準に適合し、地方厚生(支)局に届け出済みの「保険医療機関」で治療を行なう必要があります。
なかでも、顎変形症など外科手術をともなうケースでは、「顎口腔機能診断施設」として認定された医療機関での診断と治療が必須です。
また、先天性疾患が関係する症例では、「指定自立支援医療機関(育成・更生医療)」での受診が条件になる場合もあります。
いずれの場合も、治療を開始する前に、保険適用が可能かどうかを矯正専門医や医療機関に確認しておくことが重要です。
3-2. 精密検査と診断書の取得
保険適用を受けるためには、単なる「口頭の説明」だけでは認められません。
必ず、以下の手続きを踏む必要があります。
・レントゲンや模型採取などの精密検査
・医師による医学的診断書の作成
特に顎変形症の場合は、手術の必要性を医学的に証明する「顎変形症診断書」が必須です。
診断書の発行には別途費用がかかることもあるため、事前に費用や流れを確認しておくと安心です。
3-3. 保険証・紹介状など必要書類の準備
保険適用で矯正治療を受けるには、診断書のほかにも、以下のような書類が求められることがあります。
・保険証(健康保険証)
・診断書(顎変形症・対象疾患など)
・必要に応じて紹介状
・手術に関する承諾書(外科矯正の場合)
必要書類の準備は余裕を持って進めましょう。
3-4. 保険機関による診断書の審査
提出した書類をもとに、健康保険組合が審査を行ないます。書類に記載された治療の必要性や、治療内容が保険適用の条件を満たしているかが判断されます。
3-5. 審査通過後に治療開始
審査に通過すれば治療を開始します。医師の診断から治療開始までに、数週間から数ヵ月を要することもあるため、計画的に準備を進めましょう。
審査に通らなかった場合は医師と相談して、あらためて申請するか、治療方針を変更するかを検討しましょう。
4. 自由診療と保険適用で費用はどれくらい違う?

歯列矯正は「保険適用されるかどうか」で、かかる費用が大きく変わります。
ここでは、自由診療と保険適用の場合、それぞれの費用相場の違いや注意点について詳しく解説します。
4-1. 自由診療の場合の費用イメージ
自由診療で歯列矯正を行なう場合、費用は全額自己負担となります。
一般的な相場は次のとおりです。
| 矯正方法 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 部分矯正(前歯のみ) | 約10万~30万円 | 見た目の改善が主。軽度の症例向き。 |
| 表側ワイヤー矯正 | 約60万~130万円 | 従来の装置で対応力が高い。目立ちはあるが実績豊富。 |
| 裏側ワイヤー矯正 | 約100万~170万円 | 装置が目立たず審美性が高いが、費用も高め。 |
| マウスピース矯正 | 約50万~100万円 | 透明で目立ちにくく、取り外しも可能。 |
| ハーフリンガル矯正 | 約80万~150万円 | 上は裏側、下は表側で見た目とコストを両立。 |
このほか「調整料」や「保定装置代」が必要な場合もあります。
ワイヤー矯正は、歯の表側または裏側にブラケットという装置を取り付け、ワイヤーを通して少しずつ歯を動かしていく治療法です。
さまざまな症例に対応できるため、広く利用されている手法ですが「見た目が気になりやすい」「食事や歯磨きにやや注意が必要」といったデメリットがあります。
マウスピース矯正は、透明なプラスチック素材のマウスピースを装着し、その形状を定期的に変えることで、歯並びを整えていく治療法です。
装着していても装置が目立ちにくく、取り外しが可能な点が魅力で、人気が高まっています。ただし「1日20時間以上装着できない場合、治療効果に影響する」というデメリットもあります。
矯正方法を選ぶ際は費用が高い・安いだけでなく、症状やメリット・デメリットを考え、ご自身に合ったものを選択することが大切です。
4-2. 保険適用された場合の費用イメージ
保険適用で歯列矯正を行なった場合、費用は一般的に自己負担3割になります。
例えば、
■精密検査費用:約3万~5万円
■矯正治療費用:約20万~30万円(自己負担分)
といった金額が目安です。
さらに、顎変形症の場合は外科手術費用も保険適用となり、自己負担額は30万~50万円前後に収まることが多くなります(※症例や医療機関により異なります)。
保険適用と自由診療についてまとめると、それぞれの矯正にかかる費用相場は以下のとおりです。
| 項目 | 保険適用矯正 | 自由診療矯正 |
|---|---|---|
| 費用負担割合 | 一般的に3割負担 | 10割負担 |
| 治療費(目安) | 約3万~30万円(自己負担分) | 約10万~170万円以上 |
| 外科手術費用 | 保険適用対象 | 基本自由診療(医院により異なる) |
| 対象症例 | 顎変形症・先天性疾患など | すべての審美目的矯正 |
関連記事
5. 保険適用されない場合でも矯正費用を抑える3つの方法

保険適用外の歯列矯正は、自己負担額が高くなる傾向がありますが、いくつかの方法を上手に活用することで、費用を抑えることが可能です。
ここでは、自由診療の矯正治療でも活用できる3つの費用軽減策をご紹介します。
5-1. 医療費控除を活用する
自由診療の矯正でも、「噛み合わせ改善」や「機能回復」が目的と判断されれば、医療費控除の対象になります。
✅ 医療費控除のポイント
・1年間の医療費が10万円以上(または所得の5%以上)かかると控除可能
・家族分の医療費も合算OK
・確定申告で所得税・住民税の還付を受けられる
控除を受けるには、治療費の領収書や明細書の保管が必須です。
適用条件や申請方法については、国税庁の公式サイトなどで事前に確認しましょう。
関連記事
5-2. デンタルローンの利用
デンタルローンは、歯科治療専用のローンで、クレジットカードよりも低金利で長期分割がしやすいのが特徴です。
✅ デンタルローンの特徴
・長期(最長10年など)の返済が可能
・クレジットカードよりも金利が低いことが多い
・審査はローン会社によるが、歯科医院が提携しているケースも
高額な矯正治療でも月々の返済額を抑えやすく、無理のない計画が立てやすいメリットがあります。
迷った場合は、通院予定の歯科医院に「提携ローンの有無」や「具体的な金利」について相談してみましょう。
関連記事
5-3. クレジットカードで分割払いを利用する
多くの歯科医院では、クレジットカード決済に対応しています。
分割払いを活用することで、一度に大きな費用を支払わずに済みます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 手軽で手続きが簡単 | 歯科医院でそのままクレジット決済が可能 |
| ポイント・マイルが貯まる | カード会社によっては還元率が高く、旅行や買い物にも活用できる |
| 初期費用の負担軽減 | 一括払いよりも月々の出費を抑え、家計管理がしやすくなる |
※注意点として、分割払いは手数料や金利が発生する場合があるため、あらかじめ返済計画を立てておきましょう。
6. 保険適用を目指す前に知っておくべき2つの注意点

歯列矯正で保険適用が可能な場合でも、事前に知っておくべき「注意点」や「リスク」がいくつか存在します。
保険適用を目指すあまり、思わぬ落とし穴にはまらないように、ここで紹介するポイントをしっかり押さえておきましょう。
6-1. 保険適用のために無理な治療計画を立てない
保険適用を受けるために、本来は必要のない外科手術を希望してしまうケースがごくまれにあります。
例えば、軽度の出っ歯や受け口の場合、外科手術をともなわない矯正(=自由診療)で十分に改善可能なケースもあります。
しかし「費用を抑えたい」という理由だけで手術を望むと、身体への負担や治療の長期化・後悔につながるリスクがあります。
また、健康保険が適用されたとしても、「医学的な基準」によって治療方針がある程度制限されるため、自分が希望する仕上がりと異なる可能性もあります。
大切なのは、費用の負担よりも、自分にとって最適な治療を選ぶこと。
必ず信頼できる矯正専門医と相談し、メリット・デメリットをしっかり理解したうえで判断しましょう。
6-2. 保険適用に必要な手続きや書類は煩雑
保険が適用される矯正治療には、一定の診断基準と、厳密な申請手続きが必要です。
具体的には、
・指定医療機関での受診
・精密検査・レントゲン・口腔内模型の作成
・医師による診断書の発行
・紹介状や同意書の提出
など、多くのステップと書類が求められます。
また、保険適用の可否判断や事務手続きには数週間〜1ヵ月月以上かかることもあり、「すぐに治療を始めたい」という方にとってはストレスになる可能性もあります。
手続きの手間と、自由診療で得られる治療の自由度やスピードを比較して、無理に保険適用を狙わない判断も大切です。
7. 歯列矯正の保険適用に関するよくある質問

歯列矯正の保険適用に関しては、実際に治療を検討するなかで「マウスピース矯正も対象?」「指定医院はどこで探せる?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
ここでは、保険適用に関してよくある質問をわかりやすく解説します。
不安を解消し、自分に合った治療選択ができるよう、ぜひ参考にしてください。
Q1. マウスピース矯正は絶対に保険が使えない?
A: 基本的に、審美目的のマウスピース矯正(インビザラインなど)は自由診療です。
ただし、顎変形症などの適用条件を満たし、ワイヤー矯正と併用する場合などに限り、保険適用が認められるケースもあります。
Q2. 保険適用の医院はどこで探せますか?
A:保険適用で矯正治療を行なうには、厚生労働省が指定した保険医療機関で受診する必要があります。この保険医療機関の名簿は、地方厚生局の公式サイトに最新情報が掲載されています。
次の①から④の手順で検索しましょう。
①厚生労働省公式サイトの「地方厚生(支)局」から、該当する地域の厚生(支)局のサイトにアクセスする
②サイト内の検索枠に「施設基準届出受理医療機関名簿」と入力して検索する
③都道府県別の受理医療機関のなかから歯科のPDFを開く
④歯科のPDFのなかから「矯診」もしくは「顎診」の医療機関を探す
Q3. 保険が使えない矯正でも、医療費控除は受けられますか?
A: はい、自由診療の矯正でも「機能回復(噛み合わせ改善など)」が目的であれば、医療費控除の対象となります。
領収書は必ず保管し、確定申告で申請しましょう。
Q4. 顎変形症かどうかはどこで診断されますか?
A:初めは矯正歯科で診断を受けるケースが一般的です。
矯正歯科ではレントゲンやCT撮影を行い、噛み合わせや顎のズレなどから「顎変形症」の疑いがあるかを判断します。
ただし、保険適用で外科矯正を進める場合は、厚生労働省が指定する「顎口腔機能診断施設」での正式な診断・書類作成が必要です。
流れとしては、まず矯正歯科で相談・診断を受けたあと、必要に応じて口腔外科や指定医療機関を紹介され、保険適用の外科矯正を進める形になります。
👉 ポイント
・矯正歯科=一次診断(一般的な診察・治療計画)
・指定医療機関=保険適用のための最終診断・診断書作成
8. まとめ|歯列矯正の保険適用は条件次第!早めの相談が安心

歯列矯正は、原則として保険が適用されない自由診療であるため、費用はすべて自己負担となるのが一般的です。ただし、厚生労働省が定める先天性疾患がある場合や顎変形症など、限られたケースでは保険適用が認められます。
保険が適用されるには、厚生労働省に適合した保険医療機関で受診し、診断を受ける必要があります。
さらに、診断書や紹介状などの必要書類を保険機関に提出して、審査を受けなくてはなりません。医療機関と相談のうえ、早めに手続きを進めましょう。
一方、審美目的の歯列矯正は保険適用にはならないため、費用が高額になることがあります。そのような場合は、医療費控除やデンタルローンなどを活用して、費用を抑える工夫をしましょう。
「保険適用を狙うために、不要な手術を希望する」といった判断は、健康を損なうリスクをともないます。ご自身にとって本当に必要な治療かどうか、医療機関とよく相談してください。
歯列矯正の治療は長期にわたります。だからこそ、費用・期間・方法すべてを納得したうえで治療をスタートすることが重要です。
少しでも迷ったら、まずは保険適用の可否を含めた無料相談や初診カウンセリングを活用して、信頼できる専門医に相談しましょう。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/