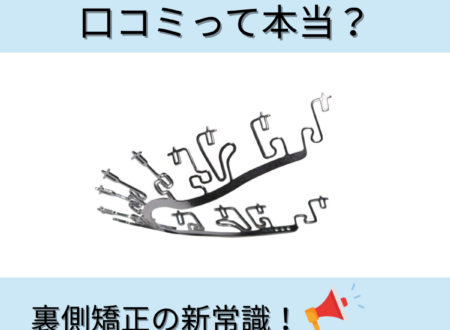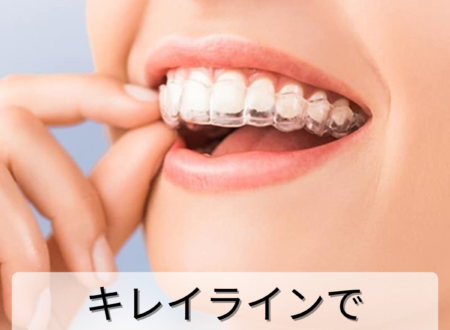- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

「マウスピース、使っていないときはどうやって保管するのが正解?」
特にマウスピース矯正中の方は、変形や劣化を避けるために保管方法に悩むことも多いのではないでしょうか。
「水に浸けっぱなしでいい?」「乾燥させるのはNG?」といった疑問に対して、
実は“水につける”保管法にも注意すべきポイントがいくつかあるのをご存知ですか?
マウスピースは保管環境によって、雑菌が繁殖したり、素材が劣化して矯正効果に影響したりする可能性もあります。
この記事では、
マウスピースを衛生的かつ安全に保つための正しい保管方法・水の使い方・NG行為・ケア方法をタイプ別にわかりやすく解説します。
毎日使うマウスピースだからこそ、正しい知識で安心して続けられるように整えておきましょう。
- 1. マウスピースは水につけて保管していいの?基本の考え方
- 2. マウスピースを水につけて保管する場合のメリット・デメリット
- 2-1. メリット:乾燥による劣化を防げる
- 2-2. デメリット:雑菌が繁殖しやすくなる
- 3. マウスピースのタイプ別|保管方法の違いに注意
- 3-1. 矯正用マウスピース(インビザラインなど)
- 3-2. ナイトガード(歯ぎしり対策)
- 3-3. スポーツ用マウスピース
- 4. マウスピースを水につけて保管する際に気をつけたいポイント
- 4-1. 使用する水の種類と品質
- 4-2. 交換頻度を守る
- 4-3. 水に浸す前の清掃
- 4-4. 保管環境の配慮
- 4-5. 定期的な点検とメンテナンス
- 5. 水以外での正しいマウスピース保管方法
- 5-1. 専用ケースで保管(通気性のあるもの)
- 5-2. ティッシュに包む保管はNG
- 5-3. 乾燥しすぎも劣化の原因に
- 6. マウスピースの衛生を保つための洗浄&ケア方法
- 6-1. 基本は「水道水+指」で洗う
- 6-2. 週に1回は専用洗浄剤で除菌
- 6-3. 超音波洗浄機を併用するのも効果的
- 6-4. NGなお手入れ方法に注意
- 7. まとめ|保管方法を見直してマウスピースを長く清潔に使おう
1. マウスピースは水につけて保管していいの?基本の考え方

マウスピースの保管方法には「乾燥させるべき」「水につけるべき」とさまざまな情報がありますが、正解は“どちらか一方”ではありません。
大切なのは、マウスピースの素材や使用目的に合わせて、適切な環境で保管することです。
たとえば、矯正用のマウスピースは比較的薄くて柔らかいため、極端に乾燥させると反りやすく、変形やひび割れの原因になります。
一方で、洗浄せずに水に浸けっぱなしにしておくと、雑菌が繁殖したり、におい・ヌメリの原因になったりするリスクも。
つまり、「水につける=清潔」「乾燥させる=安全」という単純なものではなく、
“清潔な状態で適度な湿度を保ち、過度な乾燥や水分を避ける”というバランスの取れた保管が理想なのです。
次章からは「水につける」ことによるメリット・デメリットや、マウスピースの種類別の正しい保管方法を詳しくご紹介していきます。
2. マウスピースを水につけて保管する場合のメリット・デメリット

「水につけると清潔?それとも不衛生?」マウスピースを水に浸けて保管することの良い点と注意点を、わかりやすくご紹介します。
2-1. メリット:乾燥による劣化を防げる
マウスピースは多くの場合、プラスチック製またはシリコン系の柔らかい素材でできています。
こうした素材は長時間の乾燥によって、収縮やヒビ割れ・変形が起こる可能性があります。
特に、マウスピース矯正に使われる装置は、素材のわずかな歪みが歯の移動に影響を与えるため、保管中の乾燥トラブルは避けたいところです。
その点、水に浸しておくことで乾燥によるダメージを防げるというのが主なメリットです。
2-2. デメリット:雑菌が繁殖しやすくなる
水に浸けっぱなしの状態では、雑菌やカビが繁殖しやすくなる点が最大のデメリットです。
特に、
・使用後に洗浄せずにそのまま浸けた場合
・前日の水を交換せずに放置した場合
・直射日光が当たる場所で保管している場合
などは、見た目がキレイでも細菌が増えている可能性があります。
結果として、
・不快なニオイ
・ぬめり
・マウスピースの黄ばみ
などが起こりやすくなり、衛生面でのリスクが高まるのです。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
3. マウスピースのタイプ別|保管方法の違いに注意

矯正用、ナイトガード、スポーツ用など、マウスピースには種類があります。
自分がどのタイプを使っているのかを確認したうえで、正しい保管環境を選びましょう。
3-1. 矯正用マウスピース(インビザラインなど)
使用者例:透明なマウスピースで歯列矯正を行っている方
・素材:やや柔らかめのプラスチック製(ポリウレタン系など)
・保管方法:湿度を保ちながら、通気性のある清潔な専用ケースへ
矯正用マウスピースは、変形しやすく、わずかな歪みでも歯の動きに影響するデリケートな器具です。
そのため、完全に乾燥させるのも、水に長時間浸けるのもNG。
「使用後に洗浄 → 軽く水分を拭き取り → ケースで保管」が基本の流れです。
高温・直射日光・密閉状態は避けましょう。
3-2. ナイトガード(歯ぎしり対策)
使用者例:就寝中の歯ぎしり・顎の痛み対策でマウスピースを使っている方
・素材:やや硬めのレジンやシリコン系
・保管方法:洗浄後、湿らせたガーゼやティッシュで包む/軽く湿ったケース内で保管
ナイトガードは素材がやや硬いため、乾燥によるひび割れリスクが高めです。
軽く湿らせた布で包むなどして、乾きすぎない環境を保つのが理想です。
ティッシュに直接くるんで保管すると、うっかり捨ててしまうケースも多いため注意が必要です。
3-3. スポーツ用マウスピース
使用者例:運動時に歯を保護するために使用している方
・素材:厚みのあるシリコンやエラストマー
・保管方法:洗浄後、通気性のあるケースでしっかり乾燥させる
スポーツ用マウスピースは比較的丈夫ですが、汗や唾液が付着しやすく、菌が繁殖しやすい点が特徴です。
使用後は水洗いし、しっかり乾燥させたうえでケースに入れるのがベスト。
水に浸ける保管は不要で、むしろ湿気を残すとカビの原因になることもあります。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
4. マウスピースを水につけて保管する際に気をつけたいポイント

マウスピースを水につけ続ける際には、衛生面で注意すべき点がいくつかあります。
以下にその主なポイントを詳しく解説します。
4-1. 使用する水の種類と品質
まず、水の種類とその品質が非常に重要です。
マウスピースをつける水は、飲料用の清潔な水の使用が推奨されます。
特に水道水を使用する場合は、塩素や不純物が含まれる可能性があるため、事前に濾過したり、ボイルすることが必要かもしれません。
4-2. 交換頻度を守る
つけ置き水は時間が経つと細菌や微生物が繁殖しやすくなります。
そのため、水は定期的に交換することが大切です。
目安として、最低1日1回は新しい水に取り替えることで、衛生状態を保つことができます。
4-3. 水に浸す前の清掃
マウスピースを水に浸す前には、必ずマウスピースを丁寧に洗浄しましょう。
専用のクリーナーなどを使って汚れや細菌をしっかりと落とすことで、水に浸す際の衛生リスクを大幅に軽減できます。
4-4. 保管環境の配慮
水についた状態でマウスピースを保管する際には、湿度や保管場所にも注意が必要です。
湿度が高い環境では細菌が繁殖しやすいため、通気性の良い乾燥した場所で保管するのが理想です。
また、直射日光や高温の環境を避け、清潔な専用容器を使用して保管することで、衛生的な状態を維持できます。
4-5. 定期的な点検とメンテナンス
水につけて保管している場合でも、定期的なメンテナンスを怠らないようにしましょう。
マウスピースに異常な臭い、変色、汚れが見られる場合は、すぐに清掃し、必要であれば歯科医に相談しましょう。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
5. 水以外での正しいマウスピース保管方法

マウスピースは、必ずしも「水に浸けて保管」するのが正解とは限りません。
長時間水に浸すと雑菌が繁殖したり、素材が傷む可能性も。
ここでは、水を使わずに安全に保管する方法をご紹介します。
5-1. 専用ケースで保管(通気性のあるもの)
マウスピースを保管する際は、通気性があり、湿気がこもりにくい容器を使うのが理想的です。
もし専用ケースがない場合は、市販の通気性のあるマウスピースケースや、清潔なプラスチック容器を代用しても問題ありません。
このとき、完全密閉されるタッパーやラップ、ビニール袋などは湿気がこもりやすく不衛生になりがちなので避けましょう。
使用後はしっかり洗浄し、軽く水気を拭き取ってから保管することも忘れずに。
保管中もカビや細菌が繁殖しないよう、ケースや容器自体も定期的に洗浄・乾燥しておくことが大切です。
💼 外出時のマウスピース管理に不安がある方へ
持ち運び時に便利な保管ケースや洗浄グッズなどをまとめた記事もあわせてチェックしてみてください。
👉 マウスピース矯正の持ち物&便利グッズ!外出先で快適に続けるための必需品
5-2. ティッシュに包む保管はNG
ついやりがちなのが、「洗ったあとにティッシュで包んで引き出しやバッグに入れてしまう」ケース。
この方法は以下のようなデメリットがあります:
・通気性がなく、雑菌が繁殖しやすい
・誤って捨ててしまうリスクがある
・ティッシュの繊維がマウスピースに付着することもある
短時間ならまだしも、長期の保管には不向きですので避けましょう。
5-3. 乾燥しすぎも劣化の原因に
マウスピースをむき出しのまま放置しておくと、素材がパリパリになったり、ひび割れが起こることがあります。
とくにナイトガードなどの硬めの素材では、乾燥が割れの原因になることも。
その場合は、軽く湿らせたガーゼで包んでケースに入れる、または湿度を保てるポーチで保管すると安心です。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
6. マウスピースの衛生を保つための洗浄&ケア方法

マウスピースを清潔に保つには、毎日の洗浄と適切なケアが欠かせません。
汚れを放置すると、においや黄ばみ、さらには虫歯・歯周病の原因になることも。
この章では、基本の洗い方から洗浄剤や超音波洗浄機を使ったケア方法まで、実践しやすいお手入れのコツを紹介します。
6-1. 基本は「水道水+指」で洗う
使用後は、ぬるま湯で指の腹を使ってやさしくこすり洗いするのが基本です。
歯ブラシを使う場合は、柔らかめのブラシで力を入れすぎずに行いましょう。
硬いブラシでゴシゴシこすると、表面に細かなキズができ、汚れや菌がたまりやすくなるので注意が必要です。
洗剤は使わなくてもOKですが、気になる場合は中性洗剤を少量使う程度にしましょう(漂白剤やアルコール系はNGです)。
6-2. 週に1回は専用洗浄剤で除菌
日々の手洗いだけでは落としきれない汚れや菌を除去するために、専用の洗浄剤を週に1〜2回使うのがおすすめです。
マウスピース用の発泡タイプの洗浄剤なら、水に溶かして10〜15分浸け置きするだけで除菌・消臭が可能。
使用後は水でしっかりすすぎ、自然乾燥させてから保管しましょう。
🧴 洗浄剤選びで迷っている方へ
「どんな洗浄剤を選べばいいかわからない…」という方は、実際におすすめの洗浄剤をまとめた下記の記事も参考にしてみてください。
👉 【保存版】マウスピース洗浄剤おすすめ3選!正しいケア方法と選び方を解説
6-3. 超音波洗浄機を併用するのも効果的
より徹底的に汚れを落としたい場合は、超音波洗浄機の併用も効果的です。
目に見えない微細な汚れやニオイのもとを落とすのに役立ちます。
毎日使う必要はありませんが、週に1回のスペシャルケアとして取り入れると清潔さを長く保てます。
熱湯を使用したり、洗浄時間が長すぎると素材が劣化する可能性もあるため、使用説明書の指示に従いましょう。
6-4. NGなお手入れ方法に注意
以下のような洗浄方法は、マウスピースの変形・劣化・衛生トラブルの原因になります。
・歯磨き粉をつけてゴシゴシ洗う
・塩素系漂白剤に長時間浸ける
・熱湯で消毒しようとする
・拭かずに濡れたまま密閉容器に入れる
※マウスピースは医療用のプラスチック素材でできているため、強い刺激や高温に弱い性質があります。
💡 習慣化のコツ|毎日のお手入れをルーティンに
・寝る前に外したらすぐ洗浄 → 翌朝まで自然乾燥
・朝起きたら洗浄し、その間に歯磨きを済ませる
こうした生活習慣とセットにしておくと、自然と続けやすくなります。
また、洗浄剤やケースをひとまとめにしておく「ケアセット化」もおすすめです。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
7. まとめ|保管方法を見直してマウスピースを長く清潔に使おう

マウスピースの保管は、「水に浸ければ清潔」「乾燥させれば安心」という単純なものではありません。
それぞれにメリット・デメリットがあり、重要なのは“素材や使用目的に合わせて、適切な環境で保管すること”です。
特にマウスピース矯正中の方は、変形や雑菌の繁殖によって治療の進行に影響を与えるリスクもあるため、
日々の洗浄と清潔な保管は非常に大切なポイントとなります。
記事内でご紹介したように、
・水に浸ける場合は毎日交換・事前洗浄・通気性のある保管
・乾燥させる場合は素材への負担を避け、湿度に配慮
・自分のマウスピースが矯正用・ナイトガード・スポーツ用のどれかを把握し、タイプ別に適切な方法を選ぶ
といった点を意識することで、マウスピースを清潔に保ちながら長持ちさせることができます。
また、毎日使うものだからこそ、洗浄・保管のルーティン化や、必要に応じて歯科医師への相談も大切です。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/