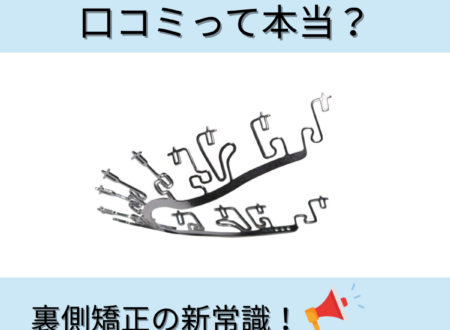- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/

「歯列矯正って必ず抜歯しないといけないの?」
歯列矯正を検討していると、インターネットや周囲の人から「矯正前に抜歯をした」という話を耳にしたことはないでしょうか。いくら歯並びを直したくても、虫歯でもない健康な自分の歯を抜きたくないと思う方もいるかもしれません。しかし実際には、抜歯をせずに歯列矯正を行なって、逆に症状が悪化してしまったというケースもあるのです。
そこで当記事では、矯正歯科治療の際に行う抜歯の必要性についてご説明します。さらに、抜歯をする歯列矯正や、抜歯をしない場合のポイントなども詳しくお伝えします。一度でも抜いてしまった歯はもとに戻りませんので、歯列矯正を検討する際はぜひ参考にしてください。
- 1. 矯正治療は抜歯が必須?非抜歯矯正との違い
- 1-1. 抜歯矯正とは
- 1-2. 抜歯矯正の流れ
- 1-3. 抜歯矯正のメリット
- 1-4. 抜歯矯正の注意点
- 1-5. 抜歯矯正のデメリット
- 2. 非抜歯矯正を選択する人も増えている
- 2-1. 非抜歯矯正とは
- 2-2. 非抜歯矯正のメリット
- 2-3. 非抜歯矯正の注意点
- 3. 矯正で抜歯が必要な場合と非抜歯が適する場合
- 3-1. 抜歯矯正の基準
- 3-1-1. 顎と歯の大きさのバランスが悪い
- 3-1-2. 上下の咬み合わせが悪い(不正咬合)
- 3-2. 非抜歯矯正の基準
- 3-3. 抜歯矯正と非抜歯矯正の費用比較
- 4. 非抜歯矯正に使用される主な装置
- 4-1. 拡大装置
- 4-2. ワイヤー矯正装置
- 4-3. マウスピース矯正装置
- 5. 矯正で抜歯した場合の輪郭や見た目の変化
- 5-1. 抜歯後に起こりうるリスク
- 5-2. 抜歯後の治療経過とケア
- 6. 抜歯矯正と非抜歯矯正:自分に最適な治療法を見つけるには
1. 矯正治療は抜歯が必須?非抜歯矯正との違い

歯列矯正を行う場合、抜歯をするのは当たり前なのでしょうか。実際には、「歯並びの乱れている程度や状態によって抜歯をするケースがある」ということになります。いずれにしても、矯正前に行う精密検査によって歯科医師や矯正医が抜歯の必要性を判断します。
1-1. 抜歯矯正とは
抜歯矯正とは、事前に抜歯をしてから行う矯正歯科治療です。歯が大きすぎたり、顎の骨が小さすぎたりする場合など、抜歯によって歯を整えるスペースを確保します。一般的には、咀嚼に悪影響を及ぼさないようにするため、犬歯の後ろにある第一小臼歯を抜歯するケースが多いです。また、さらに後ろの第二小臼歯と比較をし、虫歯の治療歴などを踏まえて健康状態の悪いほうを抜歯することもあります。
ただし、永久歯は二度と生えてはこないので、抜歯矯正を行う際は慎重に判断する必要があります。
1-2. 抜歯矯正の流れ
抜歯矯正と非抜歯矯正は、基本的な矯正期間についての流れは同じです。抜歯を行うかどうかの判断は、精密検査の結果によって治療計画を作成する際に決定します。検査によって抜歯が必要と診断された場合は、以下4.のタイミングで抜歯を行います。
1.初診(カウンセリング等)
2.精密検査
3.治療計画の立案(抜歯の判断を行う)
4.抜歯
5.矯正装置の装着
6.定期的な調整とクリーニング
7.矯正期間の終了
8.保定期間(歯の後戻りを防ぐ処置)
9.歯列矯正の完了
矯正装置を外したあとは、リテーナー(保定装置)を装着して歯の後戻りを防ぎます。特に矯正後のしばらくは歯槽骨も柔らかく、歯が元の位置に戻ろうとするため保定は非常に重要です。
1-3. 抜歯矯正のメリット
抜歯矯正のいちばんのメリットは、歯を適切な位置に移動しやすくなるという点です。特に叢生(そうせい)や出っ歯の場合など、歯が並ぶスペースが足りないことが要因の症例が多く見られます。抜歯をせずに無理に歯列矯正をした場合、歯が外側にはみ出すなどさらに悪化してしまう可能性があります。
さらに、抜歯矯正は十分なスペースが確保しやすいため、重度のガタつきなども改善しやすくなります。また、抜歯によって移動せずに済む歯が多くなった場合は、結果的に矯正期間の短縮に繋がるケースもあります。
1-4. 抜歯矯正の注意点
抜歯矯正で気になることと言えば、「自分の歯を失う」という点ではないでしょうか。噛み合わせや健康に影響がないと言われても、「せっかく健康な歯なのに」という不安を感じる方もいらっしゃいます。また、程度には個人差がありますが、抜歯後は痛みや腫れなど矯正とは関係ない不快感を伴うこともあります。そのため、抜歯矯正は信頼できる矯正医や歯科医師のいるクリニックで行うことが大切です。
また、歯列矯正は基本的には保険適用外のため、抜歯の費用も自己負担になります。金額はクリニックによって異なりますが、自費で行う抜歯の相場は1本あたり5,000~15,000円ほどです。ただし、親知らずの抜歯は保険適用となるため、1本あたり5,000円ほどで治療できます。
1-5. 抜歯矯正のデメリット
健康な歯を失うリスク
健康な歯を抜くため、心理的な負担が生じる場合があります。
顎の輪郭が変わる可能性
抜歯後の治療によって、顔の印象が変化する場合があります。
費用の増加
抜歯の処置費用や治療期間の延長により、全体的な費用が高くなることがあります。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
2. 非抜歯矯正を選択する人も増えている

これまでの歯列矯正では、歯を移動するスペースがない場合は抜歯矯正が一般的でした。しかし最近では、抜歯をせずに歯を移動する非抜歯矯正を行うケースも増えてきています。ただし、すべての症例で非抜歯矯正を選択できるわけではありません。また、非抜歯矯正にはメリットだけでなくリスクもありますので、それぞれ理解した上で行うことが大切です。
2-1. 非抜歯矯正とは
非抜歯矯正とは、抜歯をせずに歯並びを整える矯正歯科治療です。主に症状の軽い歯列の乱れや、前歯だけなどの部分矯正の場合は非抜歯矯正で改善できるケースが多いです。また、ストリッピングやIPR(歯の表面を削る処置)でスペースを確保できる場合も非抜歯で歯列矯正が受けられます。
2-2. 非抜歯矯正のメリット
非抜歯矯正における最大のメリットは、自分の歯を失わずに歯並びを改善できる点です。そのため、抜歯による痛みや不安などを感じることなくスムーズに矯正治療を開始できます。また、抜歯の費用は矯正の治療費とは別で発生することが多いため、費用面での負担も軽減されます。
2-3. 非抜歯矯正の注意点
自分の歯を残せる非抜歯矯正には、メリットだけでなく注意すべきこともあります。特に、抜歯が必要な状態なのに非抜歯で歯列矯正を行うと、以下のように様々な問題が起こる可能性があるため注意が必要です。
・出っ歯や口ゴボになる
歯が並ぶスペースが足りないと、歯列矯正をしても歯がきれいに並ぶことができません。場合によっては歯が前方に傾いてしまい、口元が盛り上がってくる可能性があります。口元が盛り上がると、口ゴボのような顔貌になってしまうリスクもあるため、非抜歯矯正には十分な注意が必要です。
・噛み合わせが悪くなる
本来の歯列矯正は、噛み合わせも考慮した上で乱れた歯並びを改善する治療です。そのため、無理に非抜歯矯正を行なった場合、歯列は整ったように見えても噛み合わせに問題が生じる可能性があります。噛み合わせの異常は、肩こりや片頭痛だけでなく顎関節症の原因にもつながります。
・歯肉退縮が起こる
スペースが足りない状態の非抜歯矯正は、場合によって歯が前方に傾いてしまうことがあります。簡単にご説明すると、3人がけのベンチに4人が座っているために、はみ出そうとしている状態です。歯が外側に傾くことで歯槽骨や歯茎も外側にズレてしまい、歯肉退縮を引き起こす可能性があります。
無理に非抜歯矯正を行なって、問題が起きてしまった場合は再矯正が必要になります。矯正のやり直しになると、結果的には抜歯をすることになるかもしれません。追加の費用もかかりますし、さらに矯正期間も伸びてしまいます。そのため、非抜歯矯正を行う際は再治療にならないよう、綿密な治療計画の上で行うことが大切です。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
3. 矯正で抜歯が必要な場合と非抜歯が適する場合

前の章では、抜歯矯正と非抜歯矯正におけるメリットと注意点について解説しました。では、歯列矯正を行う際にどのような基準で抜歯の有無を判断するのでしょうか。矯正治療を行う上で、抜歯は重要なポイントになりますのでしっかりと理解しておきましょう。
3-1. 抜歯矯正の基準
歯列矯正を行う際の抜歯の基準は、歯と顎のバランスや難症例のような歯列の乱れなど、人によってパターンが異なります。抜歯をするかどうかの明確な基準はありませんが、一般的には以下のようなケースは抜歯矯正になることが多いです。
3-1-1. 顎と歯の大きさのバランスが悪い
歯の大きさに対して顎が狭い場合、歯をきれいに並べるために必要なスペースが足りません。非抜歯矯正で無理に並べようとした場合、出っ歯や口ゴボなどの問題が生じる可能性があります。そのため、精密検査によって顎が小さいと判断した場合は、抜歯によってスペースを確保します。
3-1-2. 上下の咬み合わせが悪い(不正咬合)
奥歯の咬み合わせが悪い、または前歯の咬み合わせのズレが大きい場合も抜歯矯正になることがあります。抜歯をする歯は親知らずや第一小臼歯などが多く、歯列全体のバランスを整えながら噛み合わせを改善していきます。また、何本の抜歯を行うかは事前の検査によって決定します。
3-2. 非抜歯矯正の基準
歯の大きさと顎のバランスを見て、歯を並べるスペースが確保できる場合は抜歯をせずに歯列矯正が行えます。主に、以下のような症例については非抜歯矯正となるケースが多いです。
・前歯だけなどの部分矯正
・軽度のすきっ歯や正中線のズレ
・軽度な乱れによる全顎矯正
また、噛み合わせにも大きな不具合がなく、重度の叢生や反対咬合でない場合も非抜歯矯正で改善できるケースがあります。
3-3. 抜歯矯正と非抜歯矯正の費用比較
一般的に、非抜歯矯正は抜歯矯正よりも費用が低くなる傾向があります。非抜歯矯正では、歯の拡大装置やマウスピース矯正装置を使用することが多く、治療期間が比較的短いため、治療全体のコストが抑えられるケースが多いです。
一方で、抜歯矯正は治療の複雑さや期間の長さから、追加費用が発生する可能性があります。具体的には、以下の要素が費用に影響を与えます。
・抜歯費用
1本あたり1,000円〜3,000円(保険適用の場合)。歯科医院や抜歯の難易度によって費用が異なります。
・治療期間の延長
抜歯スペースを埋めるために、装置の調整や管理に時間がかかるため、長期間の調整料が加算されることがあります。
・追加処置費用
顎の位置調整や骨の再形成が必要な場合、追加の処置が費用に影響する場合があります。
そのため、費用面での違いを明確に把握するには、事前に治療計画書を確認し、必要な費用を詳細に見積もることが重要です。また、矯正装置の選択肢や分割払いの有無なども費用に影響を与えるため、歯科医師に相談することをおすすめします。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
4. 非抜歯矯正に使用される主な装置

通常、抜歯矯正は歯が動くスペースを確保するために行います。ただし、抜歯が不要な場合でも抜歯に代わる処置によって歯のスペースを確保するケースがあります。抜歯に代わる主な処置は以下のような方法があり、患者さんの状態に合わせて行います。
4-1. 拡大装置
拡大装置(拡大床)とは、歯列の一部や全体を拡げてスペースを生み出す装置です。拡大床は主に子供の成長期に利用されることが多いですが、大人の歯列矯正にも使われることがあります。拡大床はプレート状になっており、中央のネジを回して少しずつ歯列を外側に広げてスペースを確保します。十分に歯が並ぶスペースが確保できた場合は、抜歯をせずに歯列矯正を受けることができます。
4-2. ワイヤー矯正装置
ワイヤー矯正装置とは、歯に装着したブラケットにワイヤーを通して、少しずつ歯を移動させる矯正器具です。あらゆる症例に対応できるため、重度の叢生や出っ歯、開咬などの不正咬合にも利用できます。ただし、症状が歯並びではなく骨格に問題がある場合は抜歯矯正と併用になるケースもあります。
ワイヤー矯正装置のデメリットとして、矯正中は器具を外せないことがあげられます。そのため、虫歯や歯周病にならないよう、日々の歯みがきを念入りに行う必要があります。また、矯正器具が目立ちやすく、矯正期間中の審美性があまりよくありません。お仕事など、見た目が気になる場合は裏側矯正(舌側矯正)を選択すると良いでしょう。ただし、歯の内側に装着する手間や調整の難易度が高いため、通常のワイヤー矯正に比べて費用は割高になります。
4-3. マウスピース矯正装置
マウスピース矯正装置はアライナーと呼ばれ、歯に装着して歯列を整える透明の矯正器具です。
矯正中は、定期的に形の異なるマウスピースに交換し、少しずつ歯を移動していきます。マウスピース矯正装置は透明なので、周囲の目を気にせず治療が受けられるメリットがあります。また、自分で簡単に取り外しができるため、食事や歯みがきなどが行いやすい矯正装置です。ただし、1日20時間以上の装着が必要なので、特に睡眠時も忘れずに装着する必要があります。装着時間を守れない場合、予定通りに歯列が整わない可能性があるため注意が必要です。
また、重度の不正咬合についてはマウスピース矯正が適応しない場合があります。前後にガタガタしている重度の叢生や、顎が小さいことが要因で八重歯になっている症例などは改善できないケースが見られます。そのため、マウスピース矯正は部分矯正や軽度~中度の全顎矯正に適している矯正装置です。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
5. 矯正で抜歯した場合の輪郭や見た目の変化

必ずではありませんが、以下のような場合は抜歯によってフェイスラインが変化する可能性があります。
①親知らずの抜歯を行うと、いちばん奥の筋肉が痩せて小顔になる
②親知らずは頬骨のすぐ下にあるため、抜歯によって骨が痩せてすっきりする
③下の親知らずを抜歯するとエラ付近の骨が痩せて角ばった印象が和らぐ
親知らずを抜歯すると、歯のあった場所に負荷がかからなくなります。そのため、抜歯によって使われなくなった歯槽骨や筋肉が痩せてくることで、輪郭が変化する可能性があります。ただし、顎の骨格が原因でエラが張っている場合は、抜歯をしてもフェイスラインに変化はありません。
また、重度の叢生や出っ歯などは、抜歯によって口元が後方へ下がり、Eラインが変化する可能性があります。Eラインは「美」を表す基準で、横顔の鼻先と顎の先端を結んだラインよりも、口先がやや内側にある状態が美しいとされています。ただし日本人は鼻が低めなので、唇の先がEラインに触れる程度が理想的と判断することもあります。
5-1. 抜歯後に起こりうるリスク
矯正治療において抜歯が行われる場合、以下のようなリスクが考えられます。
・顔の輪郭が変わる可能性
抜歯による歯列の変化に伴い、特に口元や頬のラインに影響が出ることがあります。顎のスペースが減ることで、口元が引っ込み、横顔の印象が変わるケースも見られます。
・歯茎の後退
抜歯後に歯を動かす過程で、歯茎が下がるリスクがあります。特に矯正力が強すぎる場合や口腔ケアが不十分な場合に発生しやすいです。
・後戻りのリスク
治療後にリテーナーを正しく使用しないと、抜歯スペースが再び埋まり、歯列が乱れる可能性があります。これにより、矯正治療を再び行う必要が生じることもあります。
これらのリスクを最小限に抑えるためには、治療中に歯科医師の指導をしっかりと守り、定期的なチェックを受けることが重要です。
5-2. 抜歯後の治療経過とケア
抜歯後の治療経過は、個々の症例や治療計画によって異なりますが、以下のような一般的な流れが含まれます。
・抜歯直後
抜歯後は痛みや腫れが生じる場合があります。冷やしたタオルで患部を冷やし、処方された痛み止めを適切に使用してください。また、抜歯当日は激しい運動やアルコールの摂取を避けるようにしましょう。
・矯正装置の装着と調整
抜歯後、矯正装置を装着して歯を動かす治療が始まります。最初の数週間は装置に慣れるまで不快感を覚えることがありますが、徐々に改善されます。
・治療中のケア
治療中は、歯と装置の間に食べ物が詰まりやすくなるため、丁寧な歯磨きとフロスの使用が必要です。また、歯科医院での定期的なクリーニングを受けることで、虫歯や歯周病のリスクを低下させることができます。
・治療後のリテーナー装着
治療が完了した後は、リテーナー(保定装置)を装着することで歯列を安定させます。リテーナーは、歯列が元に戻る「後戻り」を防ぐために非常に重要です。
抜歯矯正は、適切な計画とケアを伴えば、理想的な歯並びと美しい輪郭を実現できる治療法です。治療を検討している方は、歯科医師にしっかりと相談し、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
6. 抜歯矯正と非抜歯矯正:自分に最適な治療法を見つけるには

歯列矯正を検討する際に「抜歯は怖いし痛いかも・・」と抜歯矯正を避けたいと考える方もいるかもしれません。しかし、抜歯をせずに無理やり歯列矯正を行うと、かえって症状を悪化させてしまう可能性もあるのです。確かに抜歯は気になるかもしれませんが、本来の目的は「健康で理想的な歯並びを手にすること」ですよね。
症状によりますが、抜歯矯正にも非抜歯矯正にもメリットやリスクがあります。特に、抜歯をしてしまった歯は二度と元に戻らないため注意が必要です。そのため、どちらの治療方法が自分に合っているか歯科医師と相談し、納得の上で治療を受けるようにしましょう。
また、治療計画に不安がある場合にはセカンドオピニオンの利用もおすすめです。
例えばウィ・スマイルでは、部分矯正から全顎矯正まで幅広い症例に対応しています。精密検査によって適応していないケースもありますが、口元にお悩みの方は気軽にカウンセリングを受けてみてはいかがでしょうか。
ご自身の症状に適した矯正方法で、理想とする歯並びを手に入れましょう!
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/