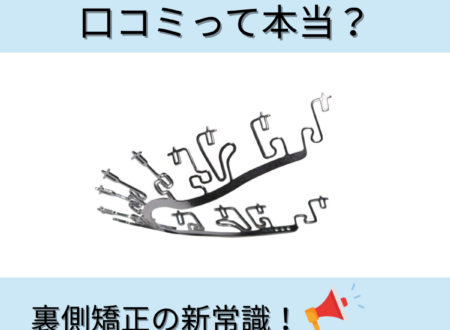- この記事の監修者
-
歯科医師。医療法人社団ピュアスマイル理事長。インビザライン ブラックダイヤモンドドクター。インビザライン世界サミット23万人いるインビザラインドクターの中からトッププロバイダーの1人に選出。
https://purerio.tokyo/
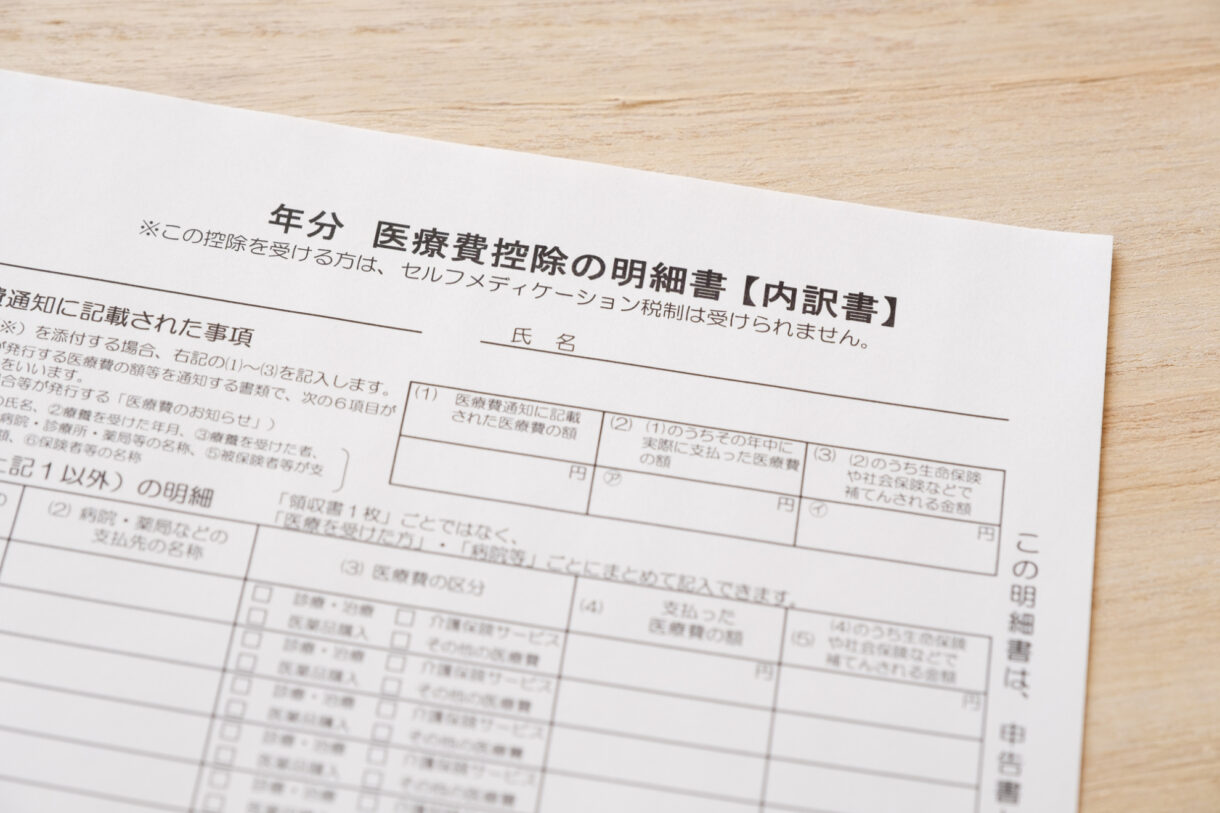
医療費を多く支払うと受けられる医療費控除ですが、歯列矯正も医療費控除の対象となるのをご存じでしょうか。
いくつかの条件を満たせば、歯列矯正でも医療費控除を受けることができます。
本記事では、医療費控除の概要や計算方法、医療費控除により戻ってくる金額のシミュレーション、申請の仕方や申請の際のポイントなどを解説します。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/
- 1. 医療費控除の計算方法
- 2. 【シミュレーション】歯列矯正の費用は医療費控除でいくら戻るのか
- ケース1:所得金額400万円、支払った医療費が60万円の場合
- ケース2:所得金額700万円、支払った医療費が100万円の場合
- 3. そもそも医療費控除とは?
- 4. 歯列矯正で医療費控除が適用される条件
- 4-1. 年間の医療費が10万円を超えている
- 4-2. 治療目的である
- 4-3. 医師の診断を受けている
- 5. 分割払いを利用しても医療費控除の対象になる?
- 6. 医療費控除の申請手続き
- 7. 医療費控除を利用する際のポイント
- 7-1. 医療費控除を利用する際のポイント
- 7-2. 5年前までさかのぼって申告できる
- 7-3. 領収書をこまめに保管する
- 8. まとめ|医療費控除を上手に利用して歯列矯正を受けましょう
1. 医療費控除の計算方法
医療費控除による還付金は、次の式で計算されます。
還付金額=医療費控除額×所得税率
医療費控除額の計算式は、以下のとおりです。
医療費控除額=支払った医療費-生命保険などで受け取った保険金-10万円(総所得金額が200万円までは総所得金額の5%)
所得税率は所得によって税率が異なります。所得別の税率を以下の表にまとめました。
| 所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 〜194万9,000円 | 5% |
| 195万〜329万9,000円 | 10% |
| 330万〜694万9,000円 | 20% |
| 695万〜899万9,000円 | 23% |
| 900万〜1,799万9,000円 | 33% |
| 1,800万〜3,999万9,000円 | 40% |
| 4,000万円〜 | 45% |
表を見るとわかるように、所得が高いほど税率は上がり、その分還付金も増えます。
したがって、医療費控除を受ける際は、家族の中で最も所得の高い人が申請するとよいでしょう。
医療費控除を申告して、実際に還付金が返ってくるのは申告してから1~1.5ヵ月後です。
ただし、e-Taxを利用してオンラインで申告を行なえば、還付までの時間はさらに短くなります。
また、医療費控除を申告すると、所得税だけでなく住民税でもメリットがあります。
ただし、住民税の場合は、翌年の住民税が所得に関係なく「医療費控除額の10%」安くなり、所得税のようにお金が還付されるわけではないため注意しましょう。
なお、医療費控除の申告手続きを行なえば、住民税の手続きをあらためて行なう必要はありません。
2. 【シミュレーション】歯列矯正の費用は医療費控除でいくら戻るのか

医療費控除によって、歯列矯正の費用は具体的にいくら戻ってくるのでしょうか。
ここでは、2つのケースでシミュレーションをしています。どちらのケースも、保険金などの受け取りはないものとし、計算を簡略化するため復興特別所得税を除外しています。
ケース1:所得金額400万円、支払った医療費が60万円の場合
まず、医療費控除額は以下のとおりです。
60万円-10万円=50万円
所得金額が400万円であれば、所得税率は20%のため、還付金額は次の式で計算できます。
50万円×20%=10万円
住民税は医療費控除額の10%安くなるため、軽減される額は以下のとおりです。
50万円×10%=5万円
したがって、所得税が10万円還付され、住民税は5万円減額されます。
ケース2:所得金額700万円、支払った医療費が100万円の場合
所得金額や支払った医療費が増えると、還付金額はどのくらい変わるのか確認してみましょう。
こちらのケースでもまず、医療費控除額を計算します。
100万円-10万円=90万円
所得金額が700万円だと、所得税率は23%になるため、還付金額は以下のとおりです。
90万円×23%=20万7,000円
住民税が軽減される金額は以下のとおりです。
90万円×10%=9万円
したがって、所得税は20万7,000円還付され、住民税は9万円減額されます。
3. そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、申告によって所得税の一部が還元される制度で、最大200万円までが控除によって還付されます。
確定申告をしない会社員や公務員であれば、すでに納めた所得税が還付金として戻り、自営業者のように確定申告をする人の場合は、確定申告で納める税金が安くなります。
さらに、所得税だけでなく翌年の住民税が安くなる点も、医療費控除のメリットです。
4. 歯列矯正で医療費控除が適用される条件

4-1. 年間の医療費が10万円を超えている
医療費控除を受けるためには、医療費を1年間に10万円以上支払っている必要があります。
ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、所得の5%以上を医療費に支払っていれば、医療費控除の対象となります。
例えば、所得が150万円であれば「150万円×5%=7万5,000円」となり、7万5,000円以上を医療費に支払っていれば控除の対象です。
なお、ここでいう医療費は、自分が支払ったものに限りません。
家族全員の医療費も対象となり、生計が同一なら離れて暮らす家族のものも合算可能です。
4-2. 治療目的である
歯列矯正で医療費控除を受けるには、治療目的でなければいけません。
例えば、以下が治療目的に該当します。
・噛み合わせが悪く、顎の痛みや頭痛に悩まされている
・発音に支障がある
・食べ物を噛みにくく、消化に悪影響がある
一方で、見た目を改善するための歯列矯正は美容目的とみなされ、医療費控除は受けられません。
4-3. 医師の診断を受けている
歯列矯正で医療費控除を受けるには、歯科医師の診断のもとで行なわれた治療でなければなりません。
大人の歯列矯正では、説明不足により治療目的ではなく美容目的だと判断される場合があります。
また、税務署から医師の診断を受けた証明として、診断書の提出を求められるケースもあります。
医療費控除を申告する際は医師の診断を受け、美容目的ではなく治療目的の歯列矯正であることを証明する診断書を用意しておきましょう。
5. 分割払いを利用しても医療費控除の対象になる?
歯列矯正では、デンタルローンなどの分割払いを利用する方も多いでしょう。
分割払いを利用したときは、1年間に実際に支払った金額のみが医療費控除の対象になります。
例えば、100万円の治療費を1年間に20万円ずつ5年間支払ったとすれば、医療費控除は1年ごとに20万円ずつ、5年間申告できます。
ただし、分割払いの金利は、医療費控除の対象にはならないため注意しましょう。
先ほども説明したように、医療費控除で戻ってくるお金は「還付金額=医療費控除額×所得税率」で計算され、所得税率は所得が多いほど高くなります。
したがって、収入に波があり、かつ資金に余裕があれば、収入が多い年をねらって一括払いにしたほうが、還付される金額は多くなります。
6. 医療費控除の申請手続き
医療費控除の具体的な申請手続きは以下のとおりです。
・必要書類の準備
・「医療費控除の明細書」の作成
・確定申告書の作成
・確定申告書の提出
まずは、医療費などで支払った領収書を集めて、10万円(総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)以上になるか確認します。
次に「医療費控除の明細書」と「確定申告書」を作成しましょう。
医療費控除の明細書や確定申告書は国税庁のWebサイトからダウンロード可能です。
なお、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の指示にしたがって入力すると、医療費控除の明細書や確定申告書を作成できるため便利です。
マイナポータルと連携すれば医療費を自動入力できるため、さらに簡単に書類を作成できるでしょう。
提出方法は、税務署の窓口・郵送・オンラインの3つがあり、先ほども説明したように、オンラインでの申告を選ぶと還付までの期間が短くなります。
7. 医療費控除を利用する際のポイント
ここからは、医療費控除を利用する際に知っておきたいポイントをいくつか紹介します。
7-1. 交通費の一部も医療費控除の対象になる
医療費控除の対象になるものには、歯科医院に支払った医療費だけでなく、通院で利用した一部の交通費も含まれます。
また、子どもの矯正治療に親が付き添ったときなど、付添人の交通費も該当します。
ただし、対象になるのは公共交通機関の利用費で、自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代、タクシー代は医療費控除の対象にはなりません。
7-2. 5年前までさかのぼって申告できる
医療費控除の申告は還付申告と呼ばれており、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間は申告することが可能です。
歯列矯正で医療費控除が受けられることを知らなかったり、申告を忘れたりしたケースでも5年前までさかのぼって申告できます。
ただし、複数年分の申告をまとめることはできないため、それぞれの年ごとに書類を作る必要があります。
7-3. 領収書をこまめに保管する
医療費控除の申告の際には、領収書の提出は必要ありません。
ただし、税務署から提出を求められるケースもあるため、5年間は保管する必要があります。
また、公共交通機関を利用したときのように領収書がないときは、利用した日付や交通機関名、かかった運賃などをメモしておきます。
メモは領収書と一緒にしっかりと保管しておきましょう。
8. まとめ|医療費控除を上手に利用して歯列矯正を受けましょう
1年間に支払った医療費が一定額以上になると医療費控除を受けられますが、歯列矯正もいくつかの条件を満たせば医療費控除の対象になります。
医療費控除で戻ってくるお金は所得税率によって異なるため、家族の中で収入が多い人が申告したり、収入が多い年に申告したりするとよいでしょう。
医療費控除を受けるには、歯科医師に治療目的であることを診断してもらう必要があります。
歯列矯正を検討しているなら、まずは信頼できる歯科医院を探して、自分に合った矯正治療を進めていきましょう。
「ウィ・スマイル」はマウスピース矯正をしたい患者さんと、全国の歯科医院を結ぶポータルサイトです。
あなたにピッタリの歯科医師を見つけたい方は、ぜひ一度ウィ・スマイルを利用してみてください。
\信頼できる矯正医を探すなら
「WE SMILE」/